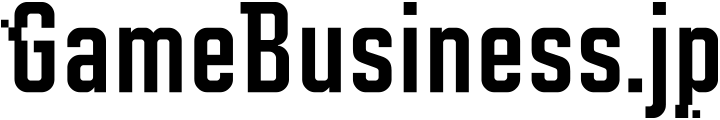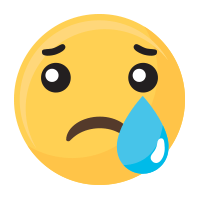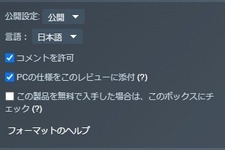また本誌の兄弟誌であるインサイドでは、その前身であるSlash Games時代から、継続的にSteamについて追い続けてきて、ちょうど10年前のValve取材記事も残されています。この当時、Steamはインディースタジオのプラットフォームというよりは、大作ゲームをエピソードごとに分けて手軽に販売したり、MODを共有するためのサービスという認識のようでした。これがわずか半年ちょっとの2008年4月にはSteam経由でリリースされた音ゲー『Audio Surf』が、実はたったひとりで作られていたということが話題になっており、本誌もそれを記事にしています。
考えてみれば、これが今のインディームーブメントの先駆けだったとも言えるでしょう。Valveの広報担当者であったDoug Lombardi氏は、その他の面白いゲームとして『Rag Doll Kung Fu』を挙げていましたが、同作開発の中心人物であったMark Healey氏がのちに『LittleBigPlanet』シリーズで知られるMedia Moleculeを創業することで、インディースタジオを表舞台に送り出すというSteamの位置づけが確立されました。
では、そんな時代からSteamは一体にどのような成長を遂げたのでしょうか? 今回は、E3 2017開催にあわせて、ロサンゼルスに滞在中だったValveのSteam担当、Ricky Uy氏、並びにBusiness DevelopmentのDJ Powers氏を直撃。たっぷりお話を伺いました。
===== ===== =====
■2016年に4,000タイトルがリリースされたSteam。その7割はインディー

Ricky Uy氏(写真左)、DJ Powers氏(写真右)
――本日はよろしくお願いします。現在Steamで作品を展開しているインディーは何社くらいなのでしょう?
Ricky Uy氏(以下Uy氏): ……とにかく、たくさん!(笑)
DJ Powers氏(以下Powers氏): 別の言い方で言うと、現在Steamで配信されているゲームはおよそ13,000本です。
――膨大なラインナップですね。
Powers氏: そのうちの半分以上は、インディーデベロッパー、独立系の会社がリリースしているタイトルですね。2016年だけで4,000本以上のゲームがリリースされて、その70%がインディー系。あくまでも感覚値ですが。
――実験的作品と言えば、これまでSteam Greenlightが重要な役割を果たしてきましたよね。
Uy氏: Steam Greenlightではこれまでおよそ5,000タイトルが正規にリリースされてきたので、それ以上の作品が申請されてきたことになります。Greenlightの成果にはすごく満足していて、この時期の目的はしっかり達成できました。そのような流れの中で6月13日にSteam Directへと移行したのは自然な流れだと思っています。
――Steam Directの詳細発表後のユーザーやメディアの反応はどうですか?
Uy氏: 非常に前向きに捉えてもらっています。Steam Directについて最初に発表してからの懸案事項は、「一体、ゲームを申請するのにいくらかかるんだ?」ということでした。特にインディースタジオにとって、初めてのタイトルを出すときはそもそも資金が無い状態からはじまります。どのような状況にあっても彼らの可能性を削いでしまうことは避けたかった。凄いゲームを作ってリリースするということを。ただ、同時にゲーム作りに対して真剣でない人たちや、Steamのシステムそのものを搾取したいと思っている人たちが手軽にシステムに入り込んでしまうことは防ぐ必要がありました。結局、リクープ可能な100ドルで落ち着いた形です。つまり、彼らが1000ドル程の収益を得た段階で、これらの料金は戻ってくることになるのです。
Powers氏: Valveの目的はデベロッパーが作りあげたコンテンツを、出来るだけ早くたくさんのお客さんの手に届けるということです。むかしはどうだったかというと……これはDougが以前話したと思いますが……Valveにいる誰かと知り合いである必要があった。そこからゲーム案をValveに申請し、Valveのほうで判断したうえで、いくつかが選ばれるというプロセスだったのです。当時、Steamの規模自体が限られていたから、これしか方法がなかったというわけです。
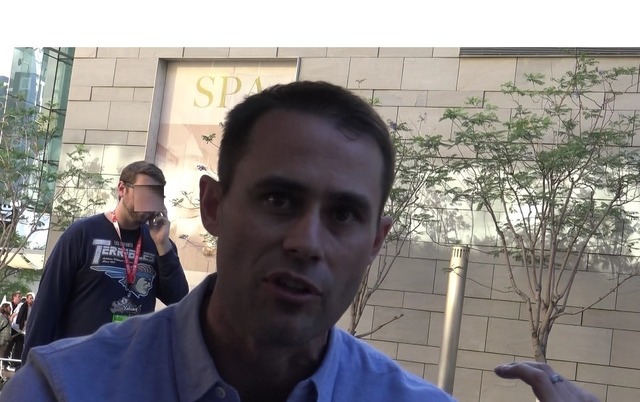
――それはSteam Greenlightが始まる前のことですね。
Powers氏: それがSteam Greenlightでは、作品の良し悪しを判断する権利をコミュニティに移譲したのです。Valve側ではそのためのパイプラインを整備することに専念しました。Steam Directは、そういった支援体制の新たな進化の段階と言えるでしょう。今回からは、開発者側と顧客との壁が可能な限り低く設定されたということです。あらゆる障壁となる可能性を取り除いて、つまりは、官僚主義的な要素を完全に取り除いた「プラットフォーム」なのです。
――官僚主義を取り除くのはなぜ重要なのでしょうか?
Powers氏: 僕たちは、よりたくさんの「ゲーム」や「アイデア」をリリースすることが出来る体制を整えることは、よりたくさんの成功体験を可能にすると思っています。世界にはたくさんの「良いアイデア」で溢れている。でも、もしValveがどのゲームをリリースするか選んでしまうと、「ある特定の顧客にとって評価されうる作品」を提供するチャンスを逃してしまうことになる。我々はSteamユーザーに「すべての作品」を提供したいのです。だから、官僚主義のようにむしろ障壁を作ってしまうプロセス自体を解消しなくてはならない。デベロッパー側にとってより手軽にコンテンツを提供できる環境をつくりたいのです。それが多くの選択の可能性を顧客に提供することになります。
※次ページ: すべてのインディーメーカーはSteamにあつまる!