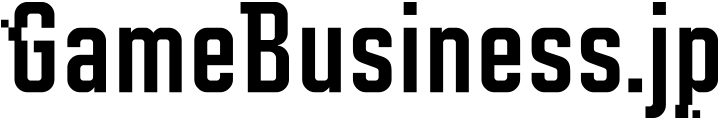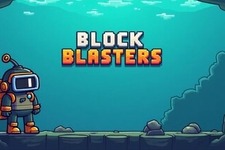「ゲームのマネタイズ」と聞いた時、何を思い浮かべますか?パッケージ購入やオンラインでのアイテム課金が一般的と思われる方も多いかもしれません。しかし近年、ブロックチェーン技術やNFTの登場により、「ゲームで遊んで資産を増やす」という新たな価値観が生まれました。
ゲームは単なる消費活動ではなく、デジタル資産を生み出す経済圏へ変化しつつあります。特に2025年は、暗号資産市場の拡大と、ゲーム内経済が外部金融と密接に連動する転換点となるでしょう。
本記事では、ゲーム業界のマネタイズ変化、デジタル資産の「所有」と「流通」の変革、ビットコインの価格変動がゲーム経済に与える影響、そして2025年以降の市場展望まで、ゲームと暗号経済が融合する最前線をわかりやすく解説します。
ゲーム業界のマネタイズはなぜ変わるのか
かつてのゲーム業界の収益モデルが限界を迎え、ユーザーの価値観が変化する中で、マネタイズの仕組みも根本から変わりつつあります。
旧来の収益モデルの限界
ゲーム業界は長らく、パッケージ販売や月額課金、そして「ガチャ」に代表されるアイテム課金によって収益を上げてきました。これらのモデルは一定の成功を収めていましたが、近年その収益性に限界が見え始めています。
また、ユーザー間でもコンテンツを一方的に享受するだけの「消費者的ユーザー体験」ではなく、より積極的にゲームの世界に関与するプレイ体験が求められるようになりました。
そして現在、一部のユーザー間ではゲーム世界で自身の「資産」を築く「投資家」としての側面が強くなっています。つまり、単なる「体験価値」だけでなく、「資産価値」をゲームに求める動きがみられるということです。
旧来のモデルでは、ユーザーが費やした時間やお金は、ゲームを離れれば基本的にゼロになっていました。しかし、デジタル資産の概念が導入されることで、その構図は根本から覆ろうとしているのです。
Web3的ビジネスモデルの台頭
こうした背景から、Web3的ビジネスモデルが急速に広まりました。特に2021年後半から2022年前半にかけては、「Play to Earn(P2E:遊んで稼ぐ)」という言葉が話題に。NFTマーケットプレイスでのアイテム売買、そしてDAO(分散型自律組織)によるゲーム運営といった新しい動きがブームを巻き起こしました。
当初は投機的な売買が先行する場面も見られましたが、現在ではそういったプロジェクトが淘汰されたにも関わらず、2025年10月時点でブロックチェーンゲームのWeb3市場占有率は27.9%と高い水準。持続可能なエコシステムの構築へと焦点が移っています。
Web3ゲーム市場を牽引しているオンラインゲーム産業は、米国市場単独で142.4億米ドル(2024年)を記録するなど、特に北米市場で高い時価総額と取引量を維持しています。日本国内においても、ゲーム業界を起点としたNFTやブロックチェーン技術の活用事例が生まれており、北米のような市場が生まれる可能性も。
Web3は単なる技術革新に留まらず、ゲーム業界のビジネスモデルそのものを変革する力として注目するべきキーワードです。
デジタル資産がもたらす“所有”と“流通”の変革
ブロックチェーン技術によってゲーム内アイテムに「所有権」が生まれ、デジタル資産が現実のお金と同様に扱われるようになった仕組みについて解説します。
ゲーム内資産が“お金”になる仕組み
ブロックチェーン技術の大きな特徴の1つが、「デジタルデータに唯一無二の所有権を与える」技術です。ゲーム内のキャラクターやアイテム、土地がデジタル資産となり、NFTが発行され、ユーザーが真の「所有者」になれる技術です。
従来は、アイテムはゲーム会社から借りているような状態で、ユーザーが完全に所有することはできませんでした。
しかしブロックチェーン技術によってユーザーはアイテムの所有者となり、アイテムの売買や貸し出しといった二次流通で利益を得られるようになったのです。
つまり、ユーザーが費やした時間やお金がデジタル資産となり、売却や運用によって収益を生み出すビジネスモデルが実現可能になったのです。
開発者・企業が得られる新しい収益源
ゲーム内アイテムの資産化は、ユーザーだけでなく、ゲーム開発者にとっても新たな収益源をもたらします。
旧来のモデルでは、アイテムの初期販売が主な収益源でしたが、NFTの二次流通においては、その都度「ロイヤリティ」として手数料を受け取ることが可能です。これにより、ゲームの人気が続く限り、開発者は永続的に収益を得られるようになりました。
さらに、将来的にはNFTのステーキング報酬や、ゲーム内トークンのDeFi(分散型金融)連携による利回り収益なども、開発者の新たなマネタイズ手法として期待されています。
つまり、ゲーム開発者がユーザーと共にゲーム内経済圏の価値を「共創」し、経済圏に参画することで恩恵を得るビジネスモデルの可能性があるということ。ユーザーが資産を形成し、その資産が活発に流通することで、開発者もまたその恩恵を受けるという、Win-Winの関係が構築されつつあります。
暗号資産の価格変動がゲーム経済に与える影響

暗号資産市場は、その特性上、価格変動が大きく、ゲーム内経済にも多大な影響を与えます。
ユーザーの行動に与える影響
暗号資産の指標となることが多いビットコイン(BTC)の価格変動が、ゲーム内のNFTやトークンの購入意欲にも影響を与えています。Web3ゲームのトークンやNFTの多くは、BTCやETH建てで価格が設定されたり、取引されたりするため、基軸通貨の価格が上昇すると、ドル建ての価値も自動的に上昇することになります。この現象が、ユーザーの「儲かっている」という心理をさらに強化するのです。
一方、価格が下落局面に入ると、投機的な取引は減少傾向に。しかし、このような状況下でも、長期的な視点を持つユーザーに信用されているプロジェクトは、価値を維持し、成長を続けられます。
ETF承認や規制緩和の効果
2024年1月には、米国でビットコイン現物ETFが承認され、機関投資家からの大規模な資金流入が期待されています。こうしたETF承認や各国の規制緩和の動きは、暗号資産の信頼性を高め、さらなる資金流入を促す可能性を生み出します。
特に2025年は暗号資産の取引が活性化する中で、ブロックチェーンゲームや関連するデジタル資産への投資も一層増加すると見られています。
そして、日本のWeb3市場において注目を集めつつあるのが、日本円連動ステーブルコインであるJPYC。JPYCは明確な法的基盤を持つことで、高い信頼性と価格の安定性を提供しており、2025年10月27日のリリース後1週間時点で総発行額は1億円を突破。価格変動リスクを懸念する一般のユーザーやWeb2の企業でも、日本円を基盤として安心してNFTやゲーム内資産を取引できると言われています。
JPYCの普及は、日本の大手ゲーム企業や一般ユーザー層のWeb3ゲーム市場への参入障壁を大きく下げ、国内で健全かつ大規模なデジタル資産経済圏を生む基盤となりうるでしょう。
ゲーム収益にもたらす影響
暗号資産の価格変動は、ゲーム開発者や運営企業にも直接的な収益影響をもたらします。
タイミング | 収益にもたらす影響 |
価格上昇時 |
|
価格下落時 |
|
キャッシュレス×暗号資産で“使いやすい資産”へ
暗号資産がより身近な存在になるためには、その「使いやすさ」が不可欠です。
2024年10月には、大手キャッシュレス決済サービスであるPayPayが、暗号資産取引所と業務提携を発表しました。この提携により、PayPayマネーを使って暗号資産を購入できるようになり、さらに暗号資産を売却した際には売却益をPayPay口座へ直接出金することが可能に。
多くの人にとって身近なPayPayの連携によって、暗号資産へのハードルが大幅に下がるでしょう。これまで興味はあっても一歩踏み出せなかった層が市場に参入しやすくなり、市場全体が大きく拡大する可能性もあります。
また、暗号資産がより身近になれば、ブロックチェーンゲーム内のトークンやNFTの売買も、より「現実の経済行動」として定着しやすくなります。
ゲーム内で得た資産をPayPayにチャージして日常の買い物に使う、あるいはPayPayからチャージした資金でゲーム内アイテムを購入するといったシームレスな体験、デジタル資産の価値をより現実的に体感できる世界が期待されます。
NFT・ブロックチェーンゲーム市場の展望とチャンス
規制整備や大手企業の参入が進む中、NFTやブロックチェーンゲームが今後どのように拡大し、どのような新たなビジネスチャンスをもたらすのかを考察します。
2025年以降の拡大トレンド
2025年以降、各国での規制整備が進み、PayPayのようなキャッシュレス決済との連携が深化することで、NFT市場の安定性と信頼性は大きく向上するでしょう。これまで様子見だった大手企業も本格的に参入しやすくなります。
実際、すでにその兆候は現れています。例えば、コナミデジタルエンタテインメントは「PROJECT ZIRCON(プロジェクト・ジルコン)」というWeb3プロジェクトを推進。カルビーはブロックチェーンゲーム「SNPIT」とのコラボレーションを実施しています。
大企業が参入する動きは、ゲーム資産が「日常利用可能な資産」としても広く認識される可能性を示しているでしょう。
新たな収益機会の広がり
ゲーム開発者は、トレンドの拡大によって二次流通におけるロイヤリティ、トークンのステーキング報酬、そしてゲーム内マーケットプレイスの手数料など、多層的かつ持続的な収益源を確立できるでしょう。
さらに、ゲームとフィンテック(金融技術)の融合は、「金融ゲーム」という新たなモデルを生み出す可能性を秘めています。金融ゲームとは、ゲームの世界に資産運用や投資、ローンといった金融要素を組み込み、ユーザーが楽しみながら経済活動を行える、より高度なエコシステムを構築するものです。
例えば、ゲーム内の土地を担保に融資を受け、その資金で新たなデジタル資産に投資するといった、現実の金融市場を模した体験がゲーム内で実現されるかもしれません。
このような進化は、ゲームが単なるエンターテイメントの枠を超え、デジタル経済の重要なインフラとして機能する未来を示しています。
まとめ
ゲーム業界では、ビットコイン価格の動向、ETF承認による機関投資家の参入、そしてPayPayのようなキャッシュレス決済インフラとの統合といった外部環境が、ゲーム産業のマネタイズ構造に大きな影響を与えています。
特に、PayPayとの連携は、暗号資産が「一部の投資家のもの」から「誰もが日常的に利用できる資産」へと進化する上で、大きなきっかけとなるでしょう。ゲーム内で培われたデジタル資産が、現実世界でそのまま消費できる未来に一歩近づいたと言えます。
時代の変化をいち早く捉え、新しいテクノロジーとビジネスモデルを積極的に取り入れた企業こそが、次世代のゲーム経済をリードし、新たな価値を創造していくことになるでしょう。