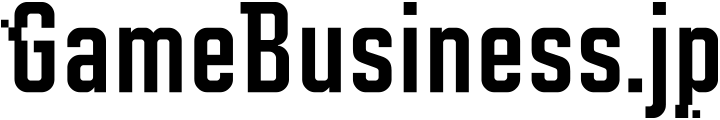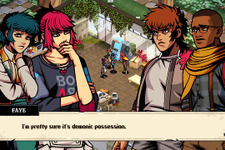2025年10月31日にスクウェア・エニックスより発売された、HD-2D版『ドラゴンクエストI&II』。本作はオリジナル版とはずいぶん戦闘バランスが異なり、特に『I』の戦闘はオリジナルでは1対1だったものから1対多となり、的確に相手の弱点や行動パターンを読んで、大量に追加された特技や持ち替え可能な装備を駆使して戦う……というテクニカルなものに変更されています。
この変更は同ゲームの「レベル上げ」の必要性とともに大きな反響を呼び、SNS上ではこの方向性の肯定も否定も含め、多様な意見が交わされています。
そこで今回はコンピューターRPG(コマンド式)の「戦闘バランス」について、さまざまな作品を例に取りながらどのようなものがあったか見ていきたいと思います。
「レベルを上げて殴ればいい」そんな時代もありました

まずはオリジナルの『ドラゴンクエストI』を見てみましょう。本作は基本的には「レベルを上げて進むゲーム」で、戦術は一部の敵に沈黙や睡眠などの状態異常が有効といった程度。レベルを上げるとより強い敵と戦えるようになり、そして一通りの武器・防具・イベントアイテムが揃うと「竜王」に挑むちょうどいい頃合いになる……SFC版のリメイク以降はそんなゲームでした(FC版は今遊ぶとレベルが上がらなさすぎる)。

初代『ファイナルファンタジー』も、基本的にはレベルを上げ、装備を強化してより強い敵に挑んでいくシンプルなRPGです。『ドラゴンクエスト』よりも属性の概念や状態異常の種類は多かったとはいえ、それらはそこまで重要視されていませんでした。
後の国産RPGの多くが『ドラゴンクエスト』『ファイナルファンタジー』をお手本としていたことを考えると、多くの国産RPGが「レベルを上げてさえいれば誰にでもクリアできる」ゲームとして認識されていくのも無理はなかったと言えます(これにはもちろん、アクションゲームやシューティングゲームなどはクリアできる人が限られていたというジャンル対比もあります)。
まるでアトラスゲーだ……と形容を作り出したほどの「アトラス」作品のインパクト

FCのRPGブームから現在に至るまで、尖ったRPGを作り続けているメーカーがあります。それが「アトラス」です。
FCの『デジタルデビル物語 女神転生』の頃から「悪魔の勧誘・合体強化」「とてつもなく複雑な属性相性」を持っており、舞台を近未来とした『女神転生II』、そして現代~ポストアポカリプスが舞台の『真・女神転生』にもそういった部分は進化して受け継がれてきました。

アトラスの個性的な戦闘バランスの極北と言えるのが、2003年に発売された『真・女神転生 III Nocturne』に搭載された「プレスターンバトル」です。敵の弱点属性を突く攻撃をすると攻撃回数が増えてより有利になり、逆に敵に弱点を突かれると敵の攻撃回数が増えてピンチに陥るという本作の特徴的なシステムは、『真・女神転生IV』『V』や『デジタルデビルサーガ アバタールチューナー』に受け継がれたほか、他のアトラス作品にも「敵の弱点を突くと戦闘が一気に有利になる」というシステムが搭載されるのが定番となりました。
この戦闘システムの導入により、単に「レベルを上げる」だけではゲームの攻略が不可能になったほか、戦闘でさまざまな属性を駆使したり、パズル的なギミック要素をバトル中に盛り込んだりするゲームが大幅に増えました。
現代でもそうした属性重視やギミック重視の高い難易度のRPGが現れると「アトラスゲーのようだ」という形容詞がしばしばゲーマーの間では用いられますし、敵に合わせた属性の対処などが求められる今回のHD-2D版『ドラゴンクエスト1』も、こうした「アトラスゲー」の影響下にある……のかもしれません。
「ロール」という概念・「ヘイト管理」という発明

「タンクが前衛に出てパーティを守り、その間にダメージディーラーがひたすら攻撃を叩き込む」……オンラインRPGでは、そんな例えが頻繁に現れます。
「ヘイト」というモンスターから狙われる頻度をゲームシステムに組み込み、「タンク」がヘイトを管理して敵の攻撃を集めている間に「ダメージディーラー」が攻撃、「ヒーラー」が回復、「バッファー」が支援……という「ヘイト管理とロール(パーティにおける役割)」をコンピューターRPGに持ち込んだのは、1999年にリリースされたオンラインRPG『EverQuest』だと言われています。
2002年リリースのオンラインRPG『ファイナルファンタジーXI』においてこのヘイト管理とロールのシステムを持ち込んだことから、国産RPGにおいても同様のシステムを持つゲームが登場しました。

またもアトラスのゲームになりますが、2007年発売の『世界樹の迷宮』におけるパラディンの挑発などはまさしく「ヘイト管理」といえるシステムですし、2009年発売の『ファイナルファンタジーXIII』では各キャラクターにアタッカー・ディフェンダー・ヒーラーなどの「ロール」を設定し、戦闘の状況に応じて切り替える「オプティマチェンジ」システムが特徴的でした。
この「ヘイト管理とロール」を組み込んだコンピューターRPGは全体的に難易度が高い傾向があります。初代『世界樹の迷宮』は言わずもがな、『FF13』も発売当初は「一本道RPG」と揶揄されましたが、戦闘の難易度はかなり高いです。これらもまた、「レベルを上げる」だけではクリアできないコンピューターRPGといえます。
余談ですが、1992年に発売された『天外魔境2』には敵を自分に向けて強制的に攻撃させる「地獄」という技があり、もしかするとこの技が国産RPGにおけるヘイト管理の最も早い登場かもしれません。
QTE……プレイヤーへの救世主となるか、面倒さの種となるか

コンピューターRPGに一味加える……そんなときによく用いられるのが、「QTE(Quick Time Event)」です。
「QTE」はRPGのみならずアクションやアドベンチャーなど、ジャンルを問わず乱発された時期があったのでこの文字列を見ただけで「ヤダーッ」となる方もいるかもしれませんが、上手く使えばゲームのアクセントとなる要素です。
そんな「QTE」をうまく活用したのが、1996年発売の『スーパーマリオRPG』でしょう。同作では「アクションコマンド」と呼ばれるQTE要素が組み込まれており、攻撃時にタイミングよくボタンを押すとダメージ増加、防御時にタイミングよくボタンを押すと完全ダメージ回避など、「使いこなすと有利になる」要素になっています。
この「使いこなすと有利になる」というのがミソで、『スーパーマリオRPG』はQTEをしなくても遊べますが、QTEを使えるとより楽しくなるゲームバランスに仕上がっています。QTEに成功する限り連続攻撃になる「スーパージャンプ」「ウルトラジャンプ」の記録目指して、頑張った方も多いのではないでしょうか。

国産ではありませんが、2025年発売の『Clair Obscur: Expedition 33』もQTEを絶妙に活用したRPGです。QTEも上手く使いこなせば、世界中で絶賛されることを証明したRPGといえるでしょう。
もっとも「QTE」は単純にゲームに組み込めばいいというものではなく、きちんと使いどころを見極めて実装しないとただ面倒になるだけなのですが(PS1初期の「ボタン連打で強くなる」と言われた某RPGを思い出しつつ)。
君はレベルを上げて楽に進めてもいいし、低レベルアタックに挑戦してもいい
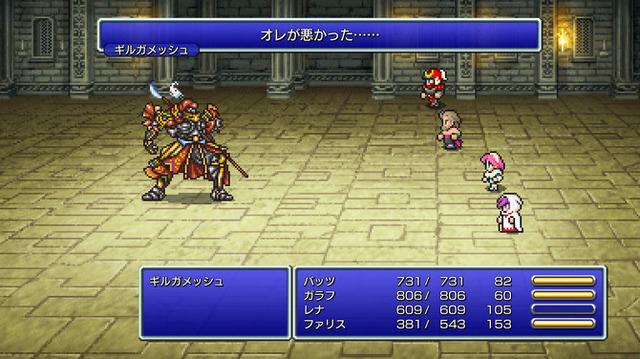
また、世の中には「低レベルクリア」へのチャレンジを想定したコンピューターRPGもあります。1992年に発売された『ファイナルファンタジーV』には「ほとんどのボス敵に経験値が設定されていない」「レベルだけでなくAP(アビリティポイント)による成長手段がある」「経験値はないがAPは落とす敵がいる」などの要素が揃っており、発売当初から現在に至るまで無数の低レベルクリアチャレンジが行われていることで知られます。
『FF5』は普通にプレイしてもギミックボスが多いのですが、その多くはレベルを上げることによってキャラクターを強くすることで突破できます。その一方で、さまざまな戦術を駆使して低レベルでボスを撃破することもできる、二面性を持ったRPGといえるでしょう。

また、2007年発売の『ファイナルファンタジーXII』インターナショナル版以降は「強くてニューゲーム」ならぬ「弱くてニューゲーム」が実装されており、こちらは敵から一切の経験値が入らず、最後まで初期レベルで通しプレイすることを求められるモードです。本作も味方の行動ルーチンを調整する「ガンビット」やさまざまなスキルを得る「ライセンス」の強化、装備品の選択によって低レベルでも敵を撃破することができるようになっており、やり込み勢の声に応えたゲームモードといえます。
RPGのゲームバランスについてまとめると、以下の3通りに分類できるかと筆者は思っています。
レベルさえ上げれば誰でもクリアまで到達できるもの
レベルを上げるだけではクリアは難しく、属性やゲームシステムの十分な理解が必要なもの
レベルを積み重ねればクリアできるが、システムの理解が深まればより快適なプレイや「やり込みプレイ」も可能なもの
1.については多くの国産RPG、2.は「アトラスゲー」に代表される高難易度なRPG、そして3.は今まで挙げた作品で言えば『スーパーマリオRPG』『FF5』が該当します。
とは言え、この3種のどれが優れていて、どれが劣っているだとかそういう話ではありません。ひりつくような高難易度RPGが好きな人もいれば、のんびりレベルを上げながら自分のペースで進められるRPGが好きだ……という人もいるでしょう。
またやり込みプレイが用意されているゲームについても、実際にそこまでやり込む人は少数でしょうし(筆者もFF5・FF12低レベルはやったことがない)、必ずしもやり込み要素が用意されていればいいというわけでもありません(コンプリート困難な実績が苦手な人もいるでしょう)。
なお、筆者が好みのタイプのコンピューターRPGは「ザコは手っ取り早く処理でき、ボスは適切な装備や戦術を揃えて互角な感じの戦いになる」ようなゲームです(つまりエクスペリエンス製RPGいいぞ!ということだ……個人の感想です)
何はともあれ、本記事をきっかけにさまざまなタイプのRPGに興味を持っていただけると嬉しいし、「分類に当てはまらない、こんな斬新なRPGもあるぞ!」という読者の皆様の声もお待ちしております。