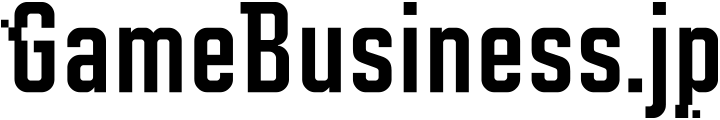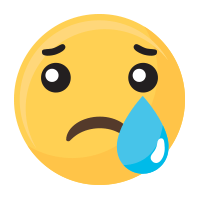2020年9月14日に講談社はインディーゲームクリエイターを支援するプロジェクト“講談社ゲームクリエイターズラボ”を立ち上げ、11月3日まで第1期のメンバーを募集しています。このプロジェクトは、半年500万円の資金提供や講談社のバックアップなど、クリエイターに提示された多くの有利な条件を特色とするもの。
そこで本稿では、Game*Spark編集部で実施した、講談社の本企画担当の鈴木氏にインタビューを行った様子をお届けします。締め切り間際での掲載となりますが、応募したいクリエイターの皆さんの役に立てば幸いです。
――今日はよろしくお願いします。自己紹介をお願いします。
鈴木綾一氏 以下、鈴木氏鈴木綾一と申します。2006年に講談社に入社しまして、週刊少年マガジンに配属され、その後ヤングマガジン編集部に異動になりまして、編集次長のほか、マンガとイラストと小説の投稿サイトをまとめる「DAYS NEO」投稿事業チームのチーム長もやっております。DAYS NEOはイラスト投稿と小説投稿のサイトもやっていてイラストコンテストなどを開催しております。
――DAYS NEOではクリエイターと編集部をつなぐマッチングの要素や自由に投稿できる仕組みができていますが、そのご経験の中からインディーゲーム支援にも取り組んでみようと思われたのでしょうか。
鈴木氏編集者として漫画家さんと取り組んでいく中、勤続15年目で講談社の強みもわかってきて、「どこに対しそれを活かせるか」と考えた時にクリエイターさんと“人間対人間”として接してきた編集者たちがいること、その編集者とクリエイターのタッグで生み出された成果物を宣伝や広報したりとか、クリエイターの才能のパブリック化を行うという意味で、最も活かせるのはインディーゲーム業界が相当するのではないか、と考えたのが経緯ですね。
――そういったことに気付いた経緯や、チームのメンバーについて教えてください。
鈴木氏ゲームは開発時間が掛かるもの、という認識はもちろんあったのですが、先日、大阪のゲーム学科も備えた専門学校の卒業制作展に漫画を拝見しに行った時に、「2年でここまで作れるようになっているんだ」っていうのが気づきとしてありました。それで「こういうこと(今回のプロジェクト)もできるんじゃないですか」と、弊社内で進言してみた所、プロジェクトチームを組成することになりました。契約関係スタッフとか、ゲームが好きなスタッフとかを含め、局とか部の垣根を越えて今7人の社員のチームとしてやっております。編集業務じゃない部署以外のメンバーが多いかな。僕が「仕事できる」と思った人を集めたっていうのが一番正直なところですね。
――ありがとうございます。鈴木さんが遊んだインディーゲームもお聞きしていいでしょうか?
鈴木氏高校生が作った『Quiet mansion』というゲームです。作者は今『AccidentHouse』いうゲームを作られていますね。漫画の場合だと、インディーと言わなくて同人と言ったりするんですけど、僕は別に同人と商業に関してそんなに違いを見出してないので面白いものは面白いと。インディーゲームでは年齢や経験関係なく面白いゲームが話題になると思うのですが、その構図は漫画や小説とすごく似てきたなという感じがしたので、我々の経験が生かせるのではないかと思います。
――応募についてお聞きしたいのですが、本数はいかがでしょう。また、デジタルのゲームとアナログのゲームの応募状況も教えてください。
鈴木氏私たちの応募はデジタルやアナログを区別していないのですけど、アナログゲーム界隈は今回の企画に対して非常に盛り上がっておりまして、応募もかなり多いですね。(全体の)応募状況でいうと、目標は100だったんですけど、今は200を超えております。最終的に500ぐらい行くのではないかと思います。思ったよりえらいことになったなと思っております。今回の企画で、一緒にやっていくことになった方に「応募して良かった」と思ってもらえるように頑張ります。
――かなりの応募があるのですね。想定より応募が多いわけですが、選出の件数を増やすなどのお考えはいかがでしょう?
鈴木氏変える予定はないですね。
――ゲームによって支援の方法や内容が変わっていくかと思うのですが、必要があれば採用前に連絡もされますか?
鈴木氏そうですね。応募の内容によって対応は変わります。一律なのは金額だけですね。
――ご支援のところですが、講談社がパブリッシングをする際に権利のところは別にして講談社の名前でリリースをされるのでしょうか。
鈴木氏凄く厳密に言うと、「できるようにしておく」っていう感じにしていまして、そのゲームの性質上、弊社単独よりも他のパブリッシャーと協力した方が良い場合もありますから、そこは本当に語義通り臨機応変に考えています。
――柔軟な対応ができるようにされているのですね。応募されているゲームのジャンルに偏りはあるのでしょうか。
鈴木氏ジャンルはバラバラですね。本当に偏りがなくって、「こんなにバラけるの!?」っていうぐらいバラけていて嬉しいです。
――募集の間口を広く取っていらっしゃったので、それが生きた形ですね。まだまだ頑張って応募してほしいところですね。海外からの応募はいかがでしょう。
鈴木氏少ないですが、ゼロではないですね。海外にも試みが伝わっていればもっと応募があったのかなと思いました。
――デジタルのゲームに限定した話になりますが、モバイルとコンシューマーやPCの割合はいかがでしょう。
鈴木氏モバイルやアプリの方が若干少ないかなという感じですね。
――講談社のIPを使いたいという応募の状況はいかがでしょう。
鈴木氏思ったより少ないですかね。ゼロではないです。
――このIPの範囲もすごく広いと思いますが、講談社のIPならなんでも利用できるのでしょうか?
鈴木氏原作者さんがノーって言ったら無理ですけど、少なくとも僕らは交渉に行きます。IPでいうと、「遊戯王」みたいにゲーム性とIPが綿密に結び付いているものが理想ですね。
――なるほど。例えばアダルトなゲームの応募が来た場合はどうされているのでしょう。
鈴木氏特にレーティングは設けていないですが、どうするのかはクリエイターさんとの話し合いですね。この企画って鏡のような存在だと思っていて、我々は特に制限を設けていないので、それぞれの方が所属している環境に応じて、いろいろな見え方をするんだと思います。例えば、ボードゲームを作っている人にとっては「ボードゲームをめちゃくちゃ支援するため企画じゃないか!」とか、デジタルゲームを作っている人が「ラッキー!」と感じてくれていたりという反響もありますね。
――ゲームというものを広くとらえていらっしゃる募集だなと感じました。鏡のような存在というのは仰る通りだと思いました。デジタルのゲーム開発だと開発支援金の、「半年で500万円」というのはエンジニア1人分くらいかなと思っていたのですが、それはデジタルのゲーム会社の視点なのでしょうね。企画のどういったところを見ておられるのでしょう?
鈴木氏企画そのものよりも、興味を惹かれるクリエイターさんと長く付き合えるか「人物を見る」という部分がかなりあると思います。漫画の場合、編集が担当をしたいって名乗りを上げる時は「クリエイターの目標に共感ができて、講談社が手助けできるいう自信がある場合に限る」っていうルールがあるんですよ。だから、「ある種もったいないな」とか、「困ってるから手助けが欲しい」っていうのが明確にあって、クリエイターの思想とか理想に共感できていれば僕らは手伝いたいですね。
――ある意味メンバーのひとりになる。というのが近いかもしれないですね。
鈴木氏そうですね。開発メンバーではなくてチームとしてのバックエンドやマネージャーが近いですね。開発ではちょっとどうにもならないところを助けてくれるメンバーのひとりだと思ってもらえるといいかなと。我々だと取材を手伝ったりとかもできますね。
――バックヤードとしての強みをお聞きしてよいでしょうか。
鈴木氏僕らは自分をプロフェッショナルじゃなくてゼネラリストの集団だと思ってるんですけど、プロフェッショナルに連絡網があるってことが最大の強みだと思ってて、例えば「刑務所の中の写真を明日までに撮ってこい」と言われると僕らは撮ってこられます。講談社には週刊現代とか週刊誌もあって、いろいろな出版をやってきているので、多分大体のものについて僕らが著作権を持った写真がありますし、ラノベ文庫も出しているので、例えばクリエイターさんがイラストレーターを必要としていれば、好みとかも聞いたうえで「この人どうですか」と提案や先方への交渉ができるので、個人ではなかなかちょっと難しいだろうなという部分に対しては結構役に立てると思っています。
――刑務所の写真を明日に用意できる…それはすごいですね。インディーゲーム開発は多様で、海外には100人くらいスタッフのいる法人もありますが、個人開発だと、異業種の会社勤めをしながら土日にがんばって2年ぐらい掛けてリリースするというケースがあるので2年間資金提供をしてもらえるのは、個人開発の方にはありがたいのかなと思いますね。
鈴木氏クリエイターさんの中にいる、本当は自分で作りたいゲームや作りかけのゲームがあるけど、親の手前とか生活もあるので就職しなきゃいけない、というような事情のある人は、この企画で年間1千万があるということになれば、親御さんの納得を得られたり、開発に専念できたりするんじゃないかと思いますね。こちらが使ってる「インディー」っていう意味としては、個人開発者が近いかなと。クリエイターさんが理想に向けてがんばっている中で、一番開発がスタックしてる原因はお金なんじゃないか、資金があると解決できることがあるのでは?と思ったので、賞金ではなく開発支援金という形にしました。例えばハイスペックパソコンが買うお金がないけど、それさえあればゲームを作れるんだ、ってクラウドファンディングをしているクリエイターさんをみたことがあって、40万円で夢を諦める人がいるんだったら何か支援したいよね。というところですね。
――人に焦点を当てるというところですが、どこを見られるのでしょう。
鈴木氏理想があって、僕たちを頼りにしてくれるかどうかだけですね。例えば、売れなくてもいいです、って言ってる人に対して僕らが売る努力をしたら迷惑になっちゃうじゃないですか。「売れたくて世界で有名になりたい。だから俺は面白いゲームを作る。よろしく!」と言ってくれたら僕らは頑張れるので。お互いに尊敬できる存在かというのも大きいかもしれないですね。言ってみれば開発に没頭するための支援です。この企画を見てラッキー!と思える人がいて、「ちょうどこういうのを作っています」って見せてもらって、我々も「めっちゃ面白いですね!」ってなって、「講談社がお手伝いするので開発よろしく!」みたいな感じに収束するといいなっていう、本当のんびりした企画だと個人的には思っています。
――ほかにも、場所の支援をしていただけるというようなことが書いておられましたが、機材の用意もいただけるのでしょうか?
鈴木氏機材は特にしないですね。
――機材は開発支援金で調達するなどすればよいでしょうね。場所の支援は、場があることで相談のしやすさとか環境を作るということですね。
鈴木氏バックエンド側としては、ゲーム開発者コミュニティ―のasobuとか、ゲーム実況の岸さんとか、色々そういうツテがあるので、そういった機会を活かすこともできます。機材に関して言えば、どういった機材やエンジン、ソフトをがいいかを聞いてくることができます。ゲームの専門家もアサインはしていて、アセット系であればその道の方に聞けば分かるので、一人で悩むよりはいいんじゃないかなと思います。
――そのほか、ゲームをリリースした後に、ゲームのコミカライズやノベライズもあり得るのでしょうか。
鈴木氏あると思いますね。
――マージンについてはどのようにお考えでしょう?
鈴木氏マージンについては公開していませんが、プラットフォームは30%というのも踏まえて色々考えています。ただし、ゼロでいいです、という気前がいい企画ではないですね。クリエイターさんと会社の関係でいえば、講談社が一番儲かる時ってクリエイターさんが一番儲かる時なんですよ。講談社が儲かれば儲かるほどクリエイターさんの手取りが減るとかでなくて、相関関係にあるので、僕らはクリエイターさんがゲームを開発したことによって、そこから映画にしたりとか。パブリッシュに関しても僕らは媒体をいっぱい持っているんで、紙媒体や電子媒体で宣伝したりと売る努力をし、ゲームに注目を集めるってことがいくらでもできます。売るためには知ってもらわないといけないので、知ってもらう努力を最大限にして、一番儲かる形にしてマージンをいただくっていう形ですね。出版を110年やってきたので、ゲームと違うところもあることは承知ですけど、本質はそんなに変わらないと思っています。
――人対人ということでは変わらないのでしょうね。知ってもらうという意味で、講談社主導での展示イベントを開催して、インディーゲームに触れる機会も作っていかれるのでしょうか。
鈴木氏やっていきたいですね。リアルのイベントがいいっていうのも、もちろん分かった上で申し上げますけど、オンラインイベントでもできるのかなと思いますね。
――講談社の手の届く範囲でこんな支援が欲しいとか、コネクション的な意味で支援が必要な時にどんどん頼っていただいて結構ですよという感じですね。
鈴木氏何でもいいから、まずは聞いてって感じですね。我々のできることってクリエイターの想像以上な部分もあると思うので、一度相談してほしいですね。無理なものは無理と言いますので。
――反対に、人に頼らないタイプのクリエイターもおられて、イラスト、プログラム、音楽など全部自分でやろうとして、すごく苦手だけど頑張って取り組んだ結果、リリースに時間がすごくかかるなんてケースもありますが、そういうクリエイターの場合どういったことができるでしょう。
鈴木氏もちろん、何も口を出さないことがクリエイターさんのメリットであれば、僕らは口を出さないです。その人の理想にまず共感できて、それをサポートすることに意義があるかどうかっていうことで。「(詰まっている部分に対し)こういう人が紹介できます、協力できます」と言っても、クリエイターさんが本当に「一ミリもいらん。自分でやる」と考えるのなら、こちらは販売と宣伝に集中します、と分業ができると思います。さらに販売も宣伝もしてくれるなと言うのだったら(企画への参加は)難しいですね。全部できる人はこの企画にむいていないかと思います。ただ、クリエイターさんと話せば、だいたいはどういう気質の人かわかるし、その上で契約するかどうかも僕らが考えるし、説得する自信もあるし、それでも無理だったら選んだこっちのせいですね。
――いろいろな質問にお答えいただき、今日はありがとうございました。
インタビュー中に鈴木氏が言われた言葉「出版社とは(クリエイターの)その才能のパブリック化」は非常に印象的で、インディーゲームが世に出ることはまさにそのクリエイターの才能のパブリック化と言えるでしょう。また、多くの個人ゲーム開発者の想像より、はるかに様々なことができるという「講談社編集部ができること」も強力なサポートになりそうです。今後、どのようなプロジェクトが採用されるのか興味は尽きません。応募は11月3日までです。