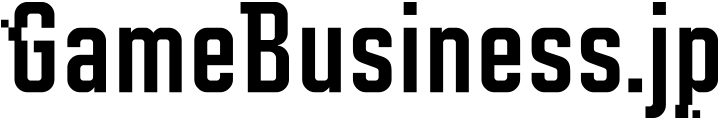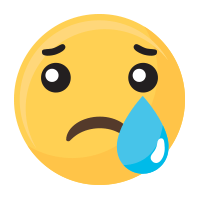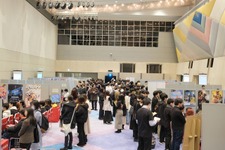安田プロデューサー単独インタビュー

2020年2月17日……マスターアップを迎え、制作の忙しさも乗り越えたかに見えたこの日こそ連続した取材の最終日であり、安田への個別インタビューが行われた日となった。市ヶ谷事業所に再び戻っての撮影だが、ディレクター兼プロデューサーとしての激動は依然として変わらず、合間を縫っての二時間一本勝負である。
安田「妖怪との戦いは『仁王』でも描けていたつもりではありました。それでも、日本にやってきたウィリアムがサムライとなっていくというストーリーが主軸だったので、サムライのアクションや戦いといった要素の方が色濃く入っていたと思います。
『仁王2』では、前作で描けていたサムライの表現は当然として、より妖怪との戦いに重きを置いたものにしようと、当初から決めて制作してきました。主人公に妖怪の力を持たせたのもそのためです。
漫画・ドラマ・映画は様々なものを参考にしました。『もののけ姫』や『千と千尋の神隠し』などはビジュアライズされた妖怪たちがたくさん出てきますし、『仁王』の時よりも更に意識して取り入れていきました。
前作はイギリスから開始するなど、西洋の要素もあったのですが、『仁王2』については日本の表現に集中しました。日本の文化や歴史といったものをより細かく調査するといったことは、『仁王』が終わった後に改めて取り組みましたね」

安田「『仁王2』でどこまで変えて、どこまで変えないかは非常に悩みました。業界に入って最初にディレクターとして携わったタイトルが『NINJA GAIDEN』だったんですが、『NINJA GAIDEN 3』の時にそれまでのハードコアなタイトルから大きく変えていきました。
メンバーが大きく変化していたというのもあるのですが、シリーズのファンの皆様から”こうじゃない!”とたくさんの批判を頂くことになるという経験があったんです。ですから、『仁王』を遊んで好きでいてくれる人達に向けて『仁王2』を制作しようと考えました。
それでも、アルファ体験版に寄せて頂いた意見の多くは”前作と何が違うんだ”というものであったのも事実です。コンセプトに立ち返って、現場で様々に相談を重ねる中で”アクションとして妖怪の要素を入れる”といったことが固まり、最終的には変えすぎず・変わらなすぎずという現在の『仁王2』に落ち着けたのかなと思います」
制作物を生み出す期間が年単位のものを世に送り出し、それが批判されてしまうその重みを想像してみることはできても、私のような一介のライターにはとても実感できるものではない。今回の取材のように、どれだけ気持ちを込めたつもりであっても、実際にかけられた時間は数日程度に過ぎないからだ。
そうした痛みを何度も受け入れてきたからこそ、『仁王2』に臨む安田文彦という”リーダー”が誕生するに至った。金子が評する通り、プレイヤーの目線に立とうとする意識は強すぎる程と言える。それがプレイヤーに媚びただけの結果に終わってしまうのかは新作をプレイしてみなければ判断できないことではあるだろう。
しかしながら、制作チームの燃えるような創作欲と、残酷となりがちなプレイヤーの冷静な視線を、自然な形で天秤に掛けて実践できるだけの「度量」がにじみ出ている人物であることは、短い取材の中でさえ私が強く感じたことのひとつであることは間違いない。

安田「実質的な作業としては『仁王』から数えると、リーダー陣も変わらず5年ほど続けていることになります。その中で私自身が驚いたこととして、『仁王2』のベータ体験版を出すことになった時、特に私が指示していなかったようなオプション機能が追加されていたりとか……間違いなくお客さんからはこんな意見がくるよね、といったことをチームが先回りして用意してくれていた点がありました。
ディレクターとして仕事をしてきた中でも、これまでなかったことだと思います。プレイヤーの皆様から指摘されるであろう利便性を自分たちで気付いて用意できるチームになってきたというのは、とても良いことだなと思いますね」
山際氏の質問に対して安田は「基本的に全てをチェックしている」と答えていた。それでも、金子や吉松の話の中からは、信頼の上において”任せる”方針を取っていたことがわかる。『仁王』のヒットからモチベーションを高めた彼らは、安田から支えられた土台によってむしろ自由に戦えることとなったのであろう。それは自発性を促し、結果的に強固な力を蓄えるに至ったのだ。

安田「『仁王2』の映像を最初に出したタイミングで、『SEKIRO』も『Ghost of Tsushima』も映像が出てきて、驚いたというのは未だに覚えてます。ただ、発売時期がそれぞれ近いというのは単なる偶然だと思っています。
どのタイトルも日本が舞台でカタナのアクションですが、見方を返せばお客さんがいないとそういうタイトルは出ないということでもあります。そうしたゲームを海外のプレイヤーも含めて多くの方が求めているというのは、正直に嬉しいことだなと感じていますね。
『仁王』はソウルシリーズの影響を明らかに受けていますので、『SEKIRO』といったタイトルは私もたくさん遊びましたし、意識していないと言えば嘘になります。チームでもファンが多くいますから、むしろ続編としての『仁王2』をしっかり作ろうよという話はしてきました」
撮影の合間にふと顔をこちらに向けて安田は言った。「インタビュアーってやってみたいんだよね。対談ってのはいやなんだけど(笑)」。明らかに疲労の色が見える中でありながら、それでも最も場を朗らかにする力を持っているのは安田であった。
スタジオジブリが好きだという安田は「作る」「伝える」「売る」というテーマを座右の銘として進んできた。『仁王2』の責任者となってから、ひたすらに対外的な仕事を重ねきたことだろう。制作の現場に集中していたディレクター時代までは、その三要素が順番にやってくるものだと思い込んでいたと言う。
しかしながら、「作る」「伝える」「売る」ことはむしろ常に同時並行であったことに気付かされたと振り返る。安田が醸し出す朗らかさは、そうした自覚によって生まれたものなのかもしれない。

安田「会社として開発メンバーを外にアピールしていくなんてルールはないです。それでも、あの二人が私に”『仁王』よかったね”と言って来ることがあり、”いや一緒に作ってたでしょ”と……。そのあたりのスタイルは変えて欲しいなという思いがありました。
実際にアートディレクター・サウンドディレクターとして二人はその実力も実績もある訳だし、しっかりお客様と向き合って発信していくディレクターであるべきだと思います。『仁王2』がはじまる時に二人にはそのように話していましたし、今回のような機会を頂いて表に出ることが二人にとってプラスになるのなら良いなと思いますね」
安田にとって金子・吉松の両者は『仁王』から共に作り上げてきた同じ目線の仲間である。それでも、リーダーに孤独はつきものなのだろう。旗印のように先陣をきらねばならない者として、『仁王2』をはじめるにあたってまず行ったことこそ、そうした仲間達を同じステージに引き上げるための”声掛け”だったのだ。
この取材を通して、安田の戦いは常にチームのひとりひとりを立たせていくことにこそあったのではなかろうかと感じられた。それぞれの将を表に立たせ、体験版という陣を張り、作戦が走り出せば信頼して任せきる。
決して煌びやかでもなければ、誰もが思わず追従してしまうようなタイプでもないのかもしれない。それでも私は、泥臭い戦い方を進める安田が『仁王2』のディレクター・プロデューサーとして立っていることで、チームの人達はどれほど心強かっただろうかと思いを馳せずにはいられなかった──。
取材が終わり、その帰り道で私は共に長期間の取材を終えたArchipelのアレックスにこう投げかけた。「なぜ日本のゲーム制作者達を映そうと思ったのか」と。
間髪入れずに氏は答える。「扉を開けたいんですよね……日本のゲーム業界の扉をこじ開けたいんです」。彼らをしてさえ、まだまだ取材の叶わぬ相手ばかりだと言う。組織的な側面を大きく持つ日本のゲーム会社は、その強さも弱さもまぜこぜにして抱え込んでいる。
それでも私は、日本のゲーム業界がこの数年で大きな危機をひとつ乗り越えたのではないかという希望を持っている。そして同時に、変化の兆しも確実に生まれているだろう。『仁王2』の彼らがありのままの姿で、その日々を私達に見せてくれたことが、その証拠であると私は信じたい。
【おことわり】
本コンテンツは、編集部とArchipelの共同オリジナル企画で制作から編集まで全て独自に行っています。制作・掲載にあたり他企業との金銭の授受は一切ありません。