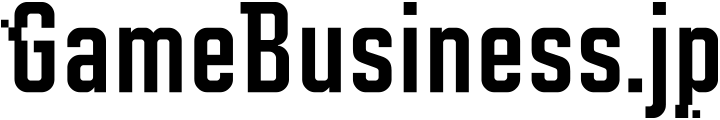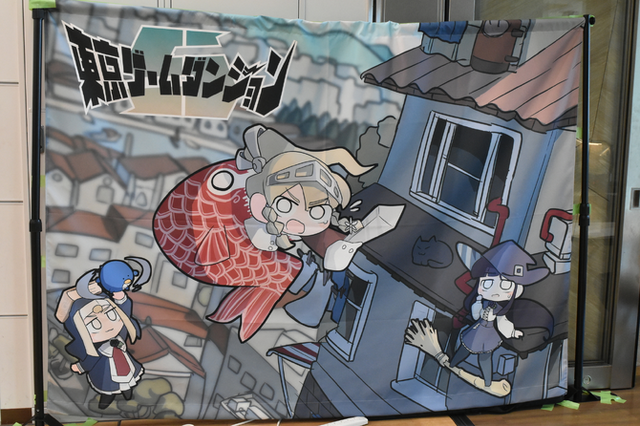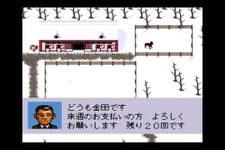2022年より開催され、今では押しも押されもせぬインディーゲームイベントとして名を馳せる「東京ゲームダンジョン」。8月には9回目の開催となる「東京ゲームダンジョン9」が開催され、盛況を博しました。記念すべき10回目となる「東京ゲームダンジョン10」も控え、さらには年末に「大阪ゲームダンジョン」も予定されています。
「愛知ゲームキャッスル」「ソウルゲームタウン」など、国内外にもインスパイアされたイベントが波及する本イベントを主催するのは、自身もゲーム開発者である岩崎氏。本稿では同氏へのインディーゲームファン必見のインタビューが実現しました。
“ゲムダン”が目指す目標や、今までに発生した困りごと、そして今後“インディーゲームが日本の文化になる”ために必要なスタンスまで、今のインディーゲームシーンのキーマンたりえる岩崎氏に気になるアレコレを聞いてきました!
“主催者が開発者”だからこそ、仲間を裏切れない。「ゲームダンジョン」誕生のきっかけなどを聞いた

―― 今回はよろしくお願いします。まずは読者の方に向けて「東京ゲームダンジョン」の説明をお願いいたします。
岩崎:「東京ゲームダンジョン」主催者の岩崎と申します。私自身、ゲーム開発を個人でやっていまして、「ゲーム開発者にとって居心地の良いイベント」を作りたいと回りの声を聴きながら作り始めました。“ゲーム開発者が楽しく作品を発表している場”を皆さんに見て、楽しんでいただけるイベントという目標で行っています。
第1回の2022年8月から、もうすぐ丸3年になります。コロナ禍の時期に始めたのですが、そこから徐々に出展者も来場者も増えてきて、「東京ゲームダンジョン9」では300団体以上に出展していただけました。本当に色んな種類のゲームが出展されるようになってきているので、来場者の方にも楽しんでいただけるイベントになっているんじゃないかと思っております。
―― コロナの時期に始まったというのは、コロナで何か意識が変わったのか、それともたまたま始めようと思っていたらコロナが来てしまったのか、どちらでしょうか。
岩崎: どちらかというと前者で、2019年から2021年までは自分はデジゲー博に出展していた側だったのですけど、2021年頃にコロナ禍が発生してオフラインイベントがオンラインに変わっていく時期になりました。
ですので「もうオフラインのイベントって終わったよね」「これからオンラインがスタンダードになっていくんじゃないか」みたいな空気が強くあったのですが、自分はオフラインイベントがすごく楽しく、続けていきたかった。大きな会社にとってオフラインイベントがリスクだとオンラインに切り替わっていくくらいなら、自分がかわりにやろうかなと考えたのがきっかけですね。
ちなみに、「東京ゲームダンジョン」1回目はコロナの上にBitSummitと日程が被り、挙げ句の果てには仏滅の日でした。「これを乗り越えたら無敵だな」と思いました。今となっては笑い話ですが当時は毎日心配で、展示会を開いてもお客さんがぜんぜん来ないという夢を何度も見ました。
―― 現在、「ゲームダンジョン」はインディーゲームイベントとしての知名度がかなり増しています。この流れは想定されていたのでしょうか。
岩崎: まったく想定していませんでした!もともと自分がやっているコミュニティ(もくもく会)の開発仲間のために立ち上げたもので、細々とアングラにやっていくつもりでした。コロナ禍のせいでオフラインイベントの機運がなくなり「定期的にコミュニティ外の人たちに発表できる場が欲しいよね」とのことで、ゲーム開発者としてプラスアルファぐらいの規模でやっていこうと思っていたんです。まさかこんなに大きくなるとは思っていませんでした。
―― ご自身では、「どのような要素が受けたんだろう」と分析されていますか?
岩崎: 開発者さまから、「こういうところが良い」とよく言われるのは、“先着順である”ことです。この形だと、「申し込めた=出展できる」わけじゃないですか。抽選だと結果がわかるまで時間差がありますし、先着順だと、何よりフェアなのです。多くの抽選も公平性を保っていると思いますが、ある種のブラックボックスでもあるので「出展者の仲の良い人を優先的に選ぶ」ことができてしまう。でも先着順だと、そういう疑いを持たれることも一切ありません。そういう透明性が受けたのだと思います。
でも実は、1回目だけは抽選にしていたのです。その時は80枠ぐらいの募集に対して120ぐらいの応募があったので、結果としてかなり落とさざるを得ませんでした。でもそれが自分にとってもすごく辛くて、せっかく申し込んでくれたのに申し訳ない気持ちになりました。ですので2回目からは先着順に変えたのです。
そして多くの来場者が来てくださっている点については、これは「自分の力」というよりは、出展者の方たちがその場で楽しみながら展示してくださって、さらにそれをSNSで発信してくださっていることが大きいでしょう。これで「面白そうだな」と多くの来場者さんが思ってくださるのだと考えています。
――開発者コミュニティ「もくもく会」は、どのような内容なのでしょうか。
岩崎:「もくもく会」は開発者たちが集まって、それぞれ自分のゲームを作っている作業会です。ゲームエンジンの縛りはなく、みんなで同じゲームを作るといったものではありません。2016年からスタートしているので、もう9年も続けていますね。
週末に実施することが多いのですが、その理由としては週末は家にいるとサボってしまって、なかなか進捗が出せないという理由です。みんな集まっている環境であれば進捗が出せるということで、毎週のようにやっています。人数は大きいところだと40人くらい、地方だと10人~20人規模でやっています。
――“主催者が開発者”だからこそ意識されている所をお聞かせください。
私は毎週のようにやっている「もくもく会」でゲーム開発者と会っているということがまずあります。そこではゲームダンジョンに関する相談もしますし、意見も聞きます。ゲーム開発者は友達であり仲間なので絶対に裏切るようなことはできないのです。
他のイベントの話を聞くと「よくも開発者にそんなひどいことができるな!」と感じることがよくありまして、当展示会と他のイベントの違いはそこにあるのかなと思います。
――「ゲームダンジョン」は “開発の進捗公開の場”と“来場者およびメディアに見せる展示会”の両側面があると思います。このバランスについてはどうお考えでしょうか。
岩崎: これがすごく難しいところで、自分も開発者なので「開発の進捗公開の場」としての展示会を想定していました。ですので開発側からしてみたら“進捗の区切り”のような意識もあるのですが、見ている側からすると、「同じ顔ぶれで進捗もどこが変わったのかわかりにくい」状況になると、どうするべきかなと思うところもあります。
年4回開催するのを決めた時も、「同じ方が連続で出展する」というのはあまり想定していませんでした。「年に1回ぐらい出展する」くらいの頻度で出られる方ばかりなんだなと思っていたら、年4回、全部出てくれるという方が多くて!
初めはそれでもいいかなと思っていたのですが、毎回出展が同じ顔ぶれ、同じ作品だと「ユーザーおよびメディアに見せる展示会」として成立しなくなるので、2点のルールを新設しました。ひとつは「過去に本展示会に出展している場合、出展作品が更新されていること」です。
あと、初めて出展される方が多くなってきましたが、そういう方は常連さんに比べて申し込み方もあまりわからないのです。先着順なので「初めて申し込みたかったのに申し込めなかった」という事態が発生してしまうのです。そこでふたつ目に「出展枠の3割程度を初出展枠にする」ルールを設けました。
これである程度、新しい方も入ってきつつも進捗公開の場として実施できるのではと思います。このように “開発の進捗公開の場”と“来場者さんおよびメディアに見せる展示会”のバランスを考えていますね。
―― 「ゲームダンジョン」に行かせてもらっている中で、途中で開発をやめざるを得なくなったゲームなどに触れたこともあります。悲しいことですが、それでも「普通にしていれば出会えないゲームとわずかにでも触れ合えた」というのがひとつの魅力だと思ってもいます。
岩崎: そうですね。さらにいうなら「拘りすぎて、リリースいつになるの!?」と思っちゃうほどの人生の力作や、普通の家庭じゃ用意できない自作コントローラーを使ったゲーム。「商業に乗せられないけど作ってみた」「作りたいから作った」みたいな作品はすごく尊くて、ここでしか遊べないタイトルだと思います。
ビジネス的な観点じゃなくて、「本当に出したかったから出した」という作品をゲームダンジョンに出してくださっているのは、主催者としてすごく嬉しいです。
―― そういった「作りたくて作る」……商業よりむしろ技術披露に特化したゲームも、「東京ゲームダンジョン」でゲーム業界の人に見られていると思うのです。「東京ゲームダンジョン」への出展が就職など「次に繋がったよ」みたいな話はありますか?
岩崎: よく聞きますね! 学生の子とかで、関係者に声をかけられて就職が決まったという話はちょこちょこ聞いています。すごく嬉しいことですね!
―― ゲームダンジョンが将来的に目指すビジョンがあればお教えください。
岩崎: 最初は「開発の進捗発表」としてゲーム開発コミュニティから始まったイベントですが、自分の考えもだんだんと変わってきました。いまでは完成してリリースされたタイトルを、すこしでも多くの人に受け入れられるようにしていきたい、みたいなところもあってSteamでの特設ページを作ったり、そういった取り組みもやってきています。
そしていずれはゲーム開発という創作活動を大衆文化にしたいと考えています。私自身がそうだったように、ゲーム、プログラムとは関係ない方にもゲーム開発に取り組んでほしいです。
あと、「ゲームダンジョン」は東京で年4回やっているのですが、今度、12月に「大阪ゲームダンジョン」を開催してみます。まずは大阪開催にチャレンジして、大阪でも安定的にできるようになったら、また別のエリアでやっていくことを構想しています。
「大阪ゲームダンジョン」「愛知ゲームキャッスル」さらには「ソウルゲームタウン」と国外にまで波及する“ゲムダン”ムーブメント
―― 「大阪ゲームダンジョン」開催に至った理由をお聞かせください。まずは、なぜ大阪を選ばれたのでしょうか。
岩崎: 元々、「東京ゲームダンジョン」は大阪から来られる方がすごく多くて、大阪でも開催してほしい要望がありました。やっぱり大阪から東京に来るとなると、泊まりが前提になったりもするので、交通費、宿泊費が結構なネックになってしまいます。ですので以前から大阪でやりたいなと思っていて、今回の出展に繋がったのです。
大阪以外では、うちによく出展してくれるヒガタニさまが名古屋でもイベントをやりたいと言われて「愛知ゲームキャッスル」が「東京ゲームダンジョン」と似たような形で今年の3月に開催されました。
その時にちょっと自分も手伝ってきたのですが、その帰りに大阪と京都のイベント会場の下見をしてきました。その時に「マイドームおおさか」という場所をみつけ、結構ここがいい会場で「ぜひここで開催したい」と思ったのも理由のひとつですね。
―― 東京開催でない苦労はありますか?
岩崎: 「ゲームダンジョン」当日は机を運ぶスタッフさんが大勢必要なのですよ。前回は30人ぐらいでしたね。机を運んだり、受付のサポートをしてもらったりしていただく必要があります。東京では日本工学院の専門学校の学生さんに集まっていただいて、ボランティアとして手伝ってもらっていますが、大阪ではそういうツテが全くないので弱りました。
そこで、大阪では106の参加枠のうち、16枠をお手伝い枠と言う形にしました。普通に出展してもらえますが、前後の机運びを手伝ってもらう代わりに出展料を無料にさせていただいて、手伝ってもらう予定です。
いずれは何年か開催して、地元の方に協力を仰げるような形式になったらいいなと考えています。あとはチラシとか機材、電源タップを東京から持って行かなきゃいけない苦労ですね。車で行く予定なので、事故らないように気をつけます(笑)。
―― お気を付けください!次回、ついに東京の方では「東京ゲームダンジョン」が記念すべき10回目になりますが、意気込みなどをお教えください。
岩崎: 「ここまできたらゲームダンジョンを100回まで続けたいね」と出展者の人たちと話してました。もちろん100回目で終わるのじゃなくて、次に目指すのは100回、という意味です。それでも、年に4回やっても25年後とかになるので、そもそも生きているのかな、となりますけど(笑)。でも、やっぱりそこまで続けていきたいと願っています。
今、愛知ゲームキャッスルを手伝ったり大阪開催も準備したりと、ちょっと頻繁にやりすぎていて、正直すこし雑になってしまっているなと内省するところもあります。
ですので100回、続けていくためにも、もう一回気を引き締め直して、開発者たちにとって、そして遊んでくださっている方たちに向け、どういう風に貢献していったらいいかともう一回考え直したいですね。
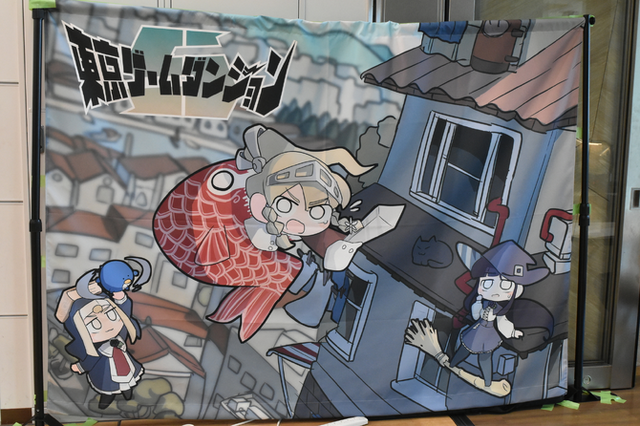
イベントとしては、もっともっとたくさんの人に来てほしいと願っています。規模を拡大させていくのもそうですし、さらにはもっと付加価値の高くしたい。そして「居心地の良いイベントにしていきたい」とも考えています。徐々に慣れが出てきてしまっている部分もあるので、改めて運営のフローを見直したいですね。
今までも1フロア開催で二日間だったり、一日開催でツーフロア開催だとか、色々な形を試してきたのですが、2日間開催とワンフロアと1日で2フロアというのを試したりもしました。地方の方からは2日間開催がいいと言われますが、年4回開催だと年間8日間も出展者の方を拘束してしまいます。
ですので今後も1日開催でやって、来年には1回だけ3フロア開催を行おうかなと思っています。ただ、単純に出展枠を増やしても来場者さんは全部回れないので、休憩スペースだったりを作る。そして3フロア開催に際しては「進捗がないと出展できない」などの部分を一旦無しにして、「ガンガン出展していいよ」という感じの物をやろうかなと考えています。
ネットで「オフラインイベントはSNSの通信簿だ」といった投稿がバズっていて、「なるほどな」と思う反面……SNSを全くやらないけど面白いゲームを作っている開発者はたくさんいます。自分の課題としては、来場者さんがいかにそういったゲームと出会ってもらえるかを考え続けることですね。
―― 東京ゲームダンジョン1回目からの変遷だったり、「思いが変化してきた」という思いを聞かせてください。
岩崎: まず、第一回目と比べるとゲームの種類の比率が変わったと感じますね。最初の「東京ゲームダンジョン」1回目はモバイル向けのゲームが多く、1つの島の全部がモバイルゲームとかだったのですが、今ではモバイルゲームがすごく減りました。今はSteamのゲーム、売り切りモデルのゲームに変わってきました。「東京ゲームダンジョン9」出展タイトルの半分以上はSteamで出していまして、これは本当に大きな変化でしたね。
また、「東京ゲームダンジョン」を始めて、東京以外の開発者の方を意識するようになりました。大阪や福岡、北海道など、自分が勝手に東京だけと視野を狭めていたのですが、当たり前ですがやっぱり全国でゲームを作っている人がいるんだなと。それで「その人たちのために何かできないかな」みたいな気持ちが生まれて、「大阪ゲームダンジョン」に繋がりました。
最近すごく多いのは、中国とか韓国から来日してでも「出展したい」といってくださる方がいるということです!もちろん日本語で話してくださります。「自分たちもゲームダンジョンに出たいですが、どうやったら出れるのですか?」と相談を受けて、「そう思ってくれているんだ!」と驚きました。

でも、残念ながら「ゲームダンジョンには日本国内の開発者ではないと出展できません」と説明させて貰っています。開発者さんの国籍はどこでも問題ないのですが、代表者の方が日本国内に住んでいなければいけない……との理由です。しかし、最近とてもよく言われるようになりました。
自分は「日本のゲーム開発シーンを盛り上げたい」との気持ちでやっているので、どこまでフォーカスしていったらいいのかという問題があります。「日本以外でもいいですよ!」とした時に、結果、“日本以外の開発者ばかり”とかになってしまったらなんだか違うかな……と思います。
どこまでを“ローカルイベントのゲームダンジョン”としてサポートしていくべきかというのは結構、悩みます。やっぱり自分もこれからもずっとゲームを作り続けていきますし、ゲーム開発者に頑張ってほしい気持ちが強いので、うまくバランスを取りながら執り行っていきたいです。
ただ、「東京ゲームダンジョン8」と「東京ゲームダンジョン9」に韓国からの来場者さんがたくさん来まして「韓国にはこういうイベントがないので羨ましい」とも言ってもらい……その後「ソウルゲームタウン」というイベントを開催することになったと言われてて、まさか自分のイベントが外国にまで波及するとは思わず、びっくりしました。
――「ソウルゲームタウン」として、韓国にまで「ゲームダンジョン」の遺伝子が波及したということですか!
岩崎: 来場された韓国の方に「どういう趣旨でこのイベントを始めたんですか」と聞かれて、趣旨や方向性を伝えるとすごく感動してくださいました。韓国ではこういうイベントが無いようなのです。
韓国だと国主導でコンテストとかをやっていて、そのコンテストに引っかからない作品は全然価値がないと見做されるようなのです。
だけどそれでも、インディーゲームを作っている人はいっぱいいます。そういう人たちの発表の場をコンテスト以外で行いたい……でも誰もやっていないんですと、話を伺いました。「なら実施すればいいじゃないですか!」とお話をしていて、自分がイベントのやり方を教える形になりました。
「東京ゲームダンジョン8」の最後に、「ソウルで絶対に実現したい」といって別れました。すると9月の中旬だったと思いますが、開催される運びになったみたいで、非常に嬉しいですね。自分は残念ながら行けないのですが、もし毎年行うのだったら、ぜひ見に行きたいと思います。
……余談ですが、その中で聞いた面白い話があります。先ほど言ったように、韓国は国主導コンテストで通らないと発表の機会を大きく失うのです。そこで、ことごとく落ちてしまった開発者さんがいて、悲しいことに自分の作品が出展できなかった。
それでその人がブチ切れて、韓国のイベントホールをひとりで貸し切ったらしいのです!自分が作ったワニをモチーフにしたゲームだけが、広い会場に展示されている、ひとりだけのインディーイベントをやったらしいんですよ。
だだっ広いところに自分1人、ソロのインディーイベント。もうめちゃくちゃ赤字だったと思いますね!それが、韓国のゲーム開発者の語り草になっているようです。
でもこれは逆に言うと、そこまでしなくちゃいけないほど抑圧されているということです。「ソウルゲームタウン」に繋がる話ですね。
――切なくも、行動力があって面白い話ですね! 国ごとの違いはやはり大きいのだと感じます。
岩崎: それでいうと、韓国と台湾の人に言われて驚いたのが「なんでゲームダンジョンはR18は扱わないんですか」ということ。コミケとかはR18の作品も出品されていますけど、「ゲームダンジョン」の一角がR18だったらすごく浮いてしまいますよね。
そもそも、うちがR18をやらない理由は都営の施設で行っているというのもあります。ゾーニングをきつくしないとダメなんですよ。それって結構イベントとしてR18出している方にとってもちょっと嫌じゃないですか。隔離されているみたいな感じでやるんだったら、もう全部R18オッケーみたいな感じでやった方がいいと思う。
――そもそも日本において、R18のゲームは「インディーゲーム」とは別のジャンルに存在している……という空気感がありますよね。確かに、インディーゲームの定義の中にあるR18作品も非常に多いのですが。
岩崎: 韓国や台湾だとそこら辺の境界線が曖昧なのかもしれませんね。
“大衆文化としてのゲーム開発”を目指す「ゲームダンジョン」
――やはり“開発者先導”としては近年では「ゲームダンジョン」が中心的な立ち位置にあると思いますが、 現在、インディーゲームイベントが増えてきた状況について感じるところや良い点、悪い点を聞かせてください。
岩崎: うちが後ろ盾もなく独立性を保ちつつも、ある程度人が集まっているというのを見ていただいて、地方でもゲームダンジョン的なイベントが増えたのかなと思っています。これはすごく良い流れだと思うんですよね。
我々だけではいろんな地方で開催できませんし、同人誌即売会みたいな形で地方でもイベントが増えていって切磋琢磨していく。そうやってどんどんインディーシーンが良くなるのは絶対良いことだと思っています。お互い、頑張っていきたいですね。今まではやっぱりイベント自体がそこまで多くなくて、出展するのも時間的、金銭的にハードルが高かった。ゲームダンジョンがそこをかなり安く設定しているのは、もっともっと大衆文化に近づいてほしい想いがあるからです。
インディーゲームイベントが増えたり、自分たちが年4回やっている中で生じる問題点は、やっぱり他のイベントと日程が被ってしまうことなのですよね。土日ってなると何かしらのイベントと被ってしまうことが多い。
それは本当に申し訳ないです。来場者さんからも「日程が被らないでほしい、どっちも行きたい」と言われたりしますが、それが結構難しくて……。うちはもう、2027年の2月開催まで日程が決まってしまっているんです。詳細な日程は近いうちに発表しようと思うんですけど。
他のイベントはうちほど頻繁にやっていないんですけど、お互い、割と先を見て予定しているのじゃないでしょうか。……そうすると、「蓋開けたら被っていた」となってしまいます。当然、意図的に被せることはしていません。そもそも、被せる意味がないのですよ!
――あえて同じ日にして来場者さんや出展者さんの奪い合い!……なんて誰も得しませんよね(笑)。
岩崎: 回避できるに越したことはないのですが、だけど主催者同士が話して日程をうまく調整できるかって……多分それも無理です。で、特にうちは開催頻度が高いので、ぶつかってしまう。
その対処策ではないのですが、今までずっと日曜日開催で行っていたのですが、少し土曜日開催を増やしてみようかなと思っています。そうすると、ぶつかっても「土曜日と日曜日でニアミス」ぐらいになるじゃないですか。今後は半分ぐらい土曜日開催にしてみたいのですよね。
土曜日の問題は、地方から泊まりで来られる方の負担が増えてしまうことで……そこも悩んでいます。
――インタビュー前に伺った“少し困った話”を、可能ならもう一度お聞かせ願いますか?
岩崎: そうですね。実は「ゲームダンジョン」を丸パクリしているイベントがあって……私は一言、「参考にさせてもらいます」などあれば良いスタンスですが、それに関しては申し込みページとか、規約の文章とか、出展マニュアル的なものまでも、私たちの文章と同じで困惑しました。
一言言ってもらえれば良いのに、私が残した誤字まで一緒でした!頑張って作り上げてきたものなので、一言も連絡なくそういうことをされるのは、さすがにいい気分はしないです。
―― 「東京ゲームダンジョン9」でビジネスチケットが追加されましたが、この意図と、導入した結果について教えてください。
岩崎: 理由は2つあります。今までは12時から17時という形で5時間やっていたのですが、今回ビジネスチケットでは11時から12時の間、1時間早く入れる形にしました。
ひとつは、出展団体数が多い中でもっと早くに入りたいという声に対応しました。今まではメディアさんのみが11時から入れるとの形にしていたのですけども、メディアさんは何百人も来るわけではないので、11時から12時の間にはもうちょっと人が入れるかなと思いました。ちょっと割高にはなるものの、パブリッシャーの方とか、ゲーム開発者さんに対して何かアプローチをしたい方に向けて、ビジネスチケットという形で一回やってみようかと考えたのです。
もうひとつ、これは結構重要な要素なのですが……迷惑な営業というか、手当たり次第に、開発者さまに関係のないビジネスをされることがありました。開発者、出展者さんが忙しくしている時に、一方的に自分の話をされて困る……みたいな自体が発生していました。
こういったイベントへの出展に慣れている方は「そういうのいいですよ」とかをすぐに言えるのですけど、うちには初めて出展される方が結構多い。ですのであまりそういうのに慣れておらず、「自分の作品を発表しに来たら、関係のない営業をかけられてすごく辛かったです」との声を結構いただくのですね。自分としてはやっぱりそういう方たちをちゃんと守ってあげたいと思っています。
ですのでビジネスチケットとして“どういう方が来られているか”ということを我々もちゃんと把握しておこうと。ビジネス目的で来られ、開発者さんに営業をされる方の名刺を頂けるようにしました。「ちゃんと管理した方がいい」との思いですね。
ですので出展者の方には、「ビジネスチケットで来場された方とは名刺を交換しておいてくださいね」という風に周知しています。あまりにも……という方には通報じゃないですけど、「名刺をもらっておいて注意する」ということをこちらからしようと思っています。
――なるほど。管理という側面でも必要だったわけですね。
岩崎: でも実際、蓋を開けてみて驚いたのは「ビジネス目的じゃないけど、1時間前に入りたいからビジネスチケットを買った」という方が結構いました。ファストパス的な使い方をされたわけですね。そういうことは需要としてあるんだなと。ちょっと意図していたところとは違う形ではあるんですけどね。
あとは、出展者の方に「11時からメディアさんが入りますよ。準備しておいてください」と言っても、間に合わなかったりで展示スペースをまだ全然準備していない方たちも多かったんですが、「ビジネスチケットも入るので11時から来場者さん入りますよ」と話をしたら、割とみんなちゃんと展示準備をしっかり完成させていて、メディアさんに取材しやすかったと言われました。
―― ずばりお伺いしますが、「東京ゲームダンジョン」において「求める支援」あるいは「要らない支援」について教えてください。今後の、周囲の人間の行動指針にもなると思います。たとえばXを見る限り“説教おじさん”もいらっしゃるようですが……。
岩崎: そうですね。上から目線で「こうした方がいい」「これがよくない」と説教する来場者の方もいらっしゃいます。ゲーム業界の人もいるのだと思うのですが、言い方の問題もあってか、それでかなり傷ついている出展者の方がいらっしゃいます。出展慣れしていない方だと、特にショックを受ける方もいます。「こんなゲーム絶対売れないよ」とか言う方もいますが、でも、そういうモノを発散する場ではないと思うのですね。
――関係性のない助言は、言い方次第で自分本位の押しつけになって、人を傷つけますからね。
岩崎: もちろん全部褒めろとは言わないのですけど、「そこまで言う必要があるのかな」ということもあります。説教おじさんは残念ながらいるみたいなんですけど、なかなか啓蒙してもそういう方はいなくならないですね。
支援という形については、日本のインディーゲームはまだ始まったばかりで、これから文化として広がっていくのかなと思っています。
その中でよくあるのは「お金を支援します」というもの。インディーゲーム開発者に対しての支援って結構多いと思うのですが、コンテストを実施してその優秀者に対してお金を渡して「開発してください」みたいなことが、多すぎるかなと思っています。
開発者側は生活費にめちゃくちゃ困っているという方ばかりではないので、それより「楽しく開発して、発表して、成長していく」流れを形成することが大事です。
――なるほど。まずは商業よりもインディーゲームを生み出す環境が大事だと。
岩崎: もちろんビジネス的視点はすごく重要ですし、日本の産業としてゲーム業界が育つのは素晴らしいことだと思います。しかしちょっと早急に、それを求めすぎている。いきなり“種を蒔いて刈り取るところ”まで求められてしまうと、ゲーム開発を楽しむ文化は萎縮してしまうのではないでしょうか。
まずは「大衆文化としてのゲーム開発」を作りあげたいので、“みんながゲーム開発を好きで、お金関係なしに発表していく”ことを温かく見守ってもらいたいし、そういう視点を持ってくださる方はすごくありがたいです。だからこそ、「具体的にどういう支援がありがたい」と言うのは難しいのですけれどね。
また、メディアさんに取り上げていただくのは嬉しい限りです。記事に取り上げていただいたり、YouTuberさんに取り上げていただいたりするのは、すごく大切な支援だと思っています。個人開発だとモチベーションが下がりぎみなので、長い目でコミュニティや開発者をサポートしてくれる場を作ってもらえると嬉しいです。
第9回では初めて「インディーライフストリーマーズ」さん、「fei CHANNEL」さんと一緒に会場から配信を行いました。出展者にも来場者にもとても喜んでいただけたので、やってよかったですね。あくまでオフラインイベントですが、イベントの外にも作品を周知できる取り組みは実施していきたいです。
たとえばサッカー大国って、やっぱり前提として「みんなサッカーが好き」という前提があるじゃないですか。そこからエースが生まれる。日本は、その最初の段階なのかなと考えています。日本の漫画産業が伸びたのは、二次創作とかも含めて「好きなものを作る」が活発になって、その中からすごい作家の方が生まれたからです。それには土壌があってこそです。「ゲームダンジョン」はそういう場所になりたいと思っています。
―― これから先、インディーゲーム市場はどう変遷されるとお考えでしょうか。
岩崎: 自分は、インディーゲームがもっともっと注目されていくのだろうなと思っています。XとかのSNSで拡散されやすいですし、逆に大手企業では、ひとりのアーティストが前面に出る作品ってなかなか難しいじゃないですか。そういう意味ではインディーゲームはどんどん伸びるはずです。今の風潮のように、Steamで作品をリリースするというケースも多くなるとは思うのですけど、僕はまだまだ他の未来、成長もあるんじゃないかなと思っていますね。
最近はタイパとかも求められたりします。今まではすごい長く100時間とかプレイするゲームだったり、繰り返しプレイするようなゲームが人気でした。しかしそれよりももっと、例えば2時間とか3時間とかで感動する映画に近いインディーゲームというものがフォーカスされるのではないでしょうか。「これ面白いな」と友人にシェアして、自分もやってみたくなる。今の時代にインディーゲームがすごく合っているんじゃないでしょうか。
もちろんAAAタイトルも存在していながら、その一方でインディーゲームしかやらない“インディーゲームファン”はもっともっと増えていくはずです。
―― 岩崎さまは「インディーゲーム」というジャンルをどう捉えて(定義されて)いらっしゃるのか、ぜひお聞きしたいです。
岩崎: やインディーゲームの定義ってやっぱりXなどでよく論争になっていますよね。『デイヴ・ザ・ダイバー』とかはインディーなのかな、みたいに。
(『デイヴ・ザ・ダイバー』の論争については開発者、ファン・ジェホ氏によりこちらのインタビューで触れられています)
個人的には、資本的にはそんなに大きくなくかつ人数としても小規模あるいは個人の方が、完全なる自分の意思、自分の判断で作っているゲームがインディーゲームだと思っています。
ただ、ゲームダンジョンの中でも結構大きな会社の新規事業でゲームを作っている方もいますし、自分が思っているというのとはちょっとずれているようなインディーゲームにも出展してもらっています。
そこの部分をどこまで広げるかというのは悩ましいのですが、できるだけ多くを包容したいので、「ぎっちぎちに東京ゲームダンジョンのルールを押し付ける」っていうのはあまりしません。ですが基本的には、「資金が少なく、小規模なチームが好き勝手やっている」みたいな、そういうものが“自分の中のインディーゲーム”ですかね。
売れたいという欲求ももちろん良いとは思うのですが、インディーゲームって、狙ってヒットするのはやっぱりすごく難しい。「売れるかどうかはさておいて、好きなものを作る」、あるいは「今まで見たことがないようなものを作る」とか、そういった精神が個人的にはすごく素敵だと感じます。
まあでも、それは自分の考えとしてはありつつ、東京ゲームダンジョンとしては「売れるためのマーケティングをしたい!」なども含めて門戸を閉じるつもりはないので、「自分はインディーゲームだと思って作っています」という考えさえ持っていればいいんじゃないかな、とも思います。

―― 最後に読者に向けてコメントをいただければ幸いです。
岩崎: 「愛知ゲームキャッスル2」を開催を皮切りに、「東京ゲームダンジョン10」が11月9日、年末の「大阪ゲームダンジョン」が12月27日に開催されます。さらには来年「東京ゲームダンジョン11」が2月に行われます。
いろんなインディーゲームを見たいという方は、ぜひ足を運んでもらえると幸いです。開発者の熱意とか、どんな考えで作品を作っているのかなど、そういったものも含めて楽しめるのがインディーゲームです。ぜひそういったものを会場で見ていただけたら嬉しいですね!
――今回は、ありがとうございました!
「東京ゲームダンジョン10」は11月9日に開催予定です。