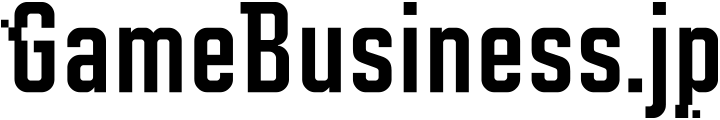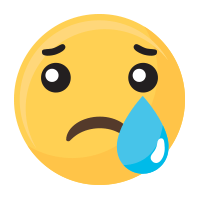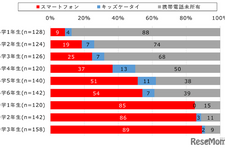2022年のBitsummit X-Roadsで意外な驚きを持って捉えられたのが、ドリコムのブースにて出展されていたタイトルでした。少しでもモバイルゲームに関心があるゲーマーであれば、同社は人気IPをもとにしたモバイルゲームの開発・パブリッシングを主な事業としているため、本イベントでもそうした事業を改めて紹介する意味合いの出展になるのではないかと予想した人も少なくないでしょう。
ところが、出展されたタイトルは同社のモバイルゲームとは真逆であり、BitSummitの会場やインディーゲームを愛するユーザーにとっても興味深いタイトルだったのです。弊誌でもレポートが公開されている『Tokyo Stories -working title-』(以下、Tokyo Stories)は、なんと買い切り型のアドベンチャーとして開発が進められているタイトルであり、同社のイメージとはまったく違ったものが展示されていたのでした。
モバイルゲームを有り体に言ってしまえば、開始から数分以内にゲームの魅力を伝え、ガチャによる強化やキャラ・アイテムなどの収集によって、運営が続く限り半永久的に遊べるものです。ところが本作についてお話をうかがうと、「プレイヤーをじっくりとゲームの世界観に引き込んでゆくスタイルで、数時間で完結する」というゲームプレイになるというではありませんか。
その他にもモバイルでの対戦格闘ゲーム『Project BEAT(仮題)』を開発しているなど、これまでと違う試みを見せています。なぜこのようなタイトル開発を行っているか、果たしてどのようなタイトルとなるのかを、ドリコムの池田佑基氏と甲斐康弘氏にうかがいました。
※インタビュー中は敬称略
インタビュイー
池田佑基氏(ゲームカンパニー プロダクト3部 部長/プロデューサー)
2013年にドリコムにジョイン。2006年~2013年まではソニー・コンピュータエンタテインメント(現・ソニー・インタラクティブエンタテインメント)に所属し、『rain』のディレクターなどを務める。ドリコム入社後は有名IPゲームの開発運営などを手掛け、2020年頃から新規オリジナルIPの立ち上げプロジェクトを開始し、今回発表された『Tokyo Stories』などのプロジェクトに携わっている。
甲斐康弘氏(ゲームカンパニー プロデューサー)
2009年よりドリコムに所属。ゲーム開発に携わるまでは着メロなどの制作やマネジメントを行ってきた。これまで携わってきたタイトルはフォワードワークスから配信されている『みんゴル』(同名シリーズのモバイル版、開発はドリコムが担当)など。2022年からはモバイル向け対戦格闘『Project BEAT(仮題)』のプロデューサーを務める。
ドリコムの方針転換が、PS3の『rain』を生み出したクリエイターの最新作と、新たなスマホ格ゲーの企画に結実
ーーお二人はもともとはモバイルゲームをメインにやってらしたわけですね。
甲斐:僕はずっとモバイルです。プロジェクトの立ち上げから携わることが多かったですね。運営も多少は関わっているんですけど、新規でリリースして数か月後にはまた新しいプロジェクトの立ち上げに移るということが多かったです。
池田:自分はドリコムに入社して9年目で、『ONE PIECE トレジャークルーズ』などの開発に携わってきました。その前はコンソール向けのタイトルをソニー・インタラクティブエンタテインメントで作っていまして、『rain』っていうゲームなんですけど……。
ーーあの『rain』を手掛けてらっしゃったんですか!言われてみると、『Tokyo Stories』も近い雰囲気を感じます。
池田:ちょっとスタイルは似ていると思います(笑)。あの時は“雨”がテーマでした。本作でアートディレクターをやっている寺島誠一くんも当時から一緒にやっている戦友ですね。
『rain』は小さく上手く作れたと思っています。だけど、大きくゲームを作りたいなあ、と思ったときに、ちょうどモバイルゲームの隆盛を横目でみながら大きなチャレンジができるのではと思ってドリコムに移ったんです。様々なタイトルに携わってきましたが、そうこうしているうちに自分の中で揺り戻しみたいなものがありました。そんな心境の変化がある中で、「またコンパクトなゲームを作りたいね」と寺島くんと喋っていて、『Tokyo Stories』へと繋がっていったんです。
ーーまず、お二人が新規IPを企画した背景についてうかがえますか。
池田:ドリコムとして「新しいIPを作っていこう」という方針になっていることが大きいです。
ゲーム事業だったらゲームを中心としたIPを、出版事業だったら出版を中心としたIPを作っていくという大きな戦略が軸にあります。そうした戦略に基づいて、自分もいくつか新規IPを立ち上げているのですが、その中で「ピクセルアートを使った、世界に通用するようなIPを作っていきたい」という思いがあり、「東京を舞台にした、小さい物語」を作ったら、世界で見てもらえるものを作れるかなと思ったのが始まりです。
甲斐:いままで外部パートナーのIPものに携わることが多かったので、やはり自分自身もゲームが好きですし、いつかはそういうオリジナルのIPを作りたいなという思いはずっとありました。長くモバイルゲームの開発を経験していると、どのくらい立ち上げまでに時間がかかって、どのタイミングでしんどいときが来るのか見えてきちゃうので、少しそういうサイクルから離れたいなと。
会社の方針も変わるタイミングでしたし、完全に新規で、小規模でやれたら楽しいよなと思って、チャレンジをしてみたいと手を挙げました。今日(BitSummit会場)は来られなかったのですが、僕が手掛ける『Project BEAT(仮題)』のディレクターが格ゲーが好きで、バトルアクション要素があり、対戦できるものを考えていたんです。彼のやりたいことと僕が新規IPにチャレンジしたい思いがうまくはまって形になり始めました。
ーー特に『Tokyo Stories』の場合、「PCでの買い切り型」として開発しているのは思い切った印象があります。
池田:最初はやっぱりスマートフォン向けに展開しようかとも考えていたのですが、ビジネス的にもゲーム的にもスマートフォン向けでは、このゲームでやりたいような小さい物語を感じさせるというのがちょっと難しいなと。運営型のタイトルにしないで、売り切りにするという方法もありますが、金額の設定が難しいといったこともありますし。
そうこう悩んでいたら「買い切りでPCもありなんじゃない?」って話をされて、ああ、確かにそうだなと。正直ドリコム=モバイルプラットフォームでという前提だったので、全然、そういった発想がありませんでした。
我々がやりたいのはゲームを作ること、そうして新しいIPを生み出していくことです。だから出し先は我々が得意としているスマートフォンだけじゃなくていいんじゃないか、というクリエイターとしての原点に立ち返り、小規模なゲームタイトルを自社でパブリッシングしていくことをいま模索しています。それが『Tokyo Stories』です。
ーーちなみに現在のコアメンバーはどれくらいの規模で開発しているのでしょうか。
池田:弊社で運営する他の運用タイトルと比べると小さいチームにはなると思います。『Tokyo Stories』は4人ですね。運用タイトルは数十人でやっているので(笑)。
甲斐:うちはいま2人くらいですね。
ーーそれを聞くだけでもこれまでのドリコムの事業と比べて異例ですね。
池田:確かにそうですね(笑)。けれど、好き勝手に色々やらせてもらっているので、やりやすい環境ではあります。
あとは少人数チームのほうが機動性も高いし、試験的にやるのも早いので、そういう意味だとコアな部分を作りこむのは少人数でやったほうがいいのかと。コンセプトもブレにくくもなるので。
『Tokyo Stories』はどんな作品になるのか?

ーー『Tokyo Stories』は試遊の段階でも作りたい方向は明確でした。あらためて本作の内容を教えていただけますか。
池田:簡単に説明しますと「3Dで作られたピクセルアートのビジュアルで、東京の街を舞台にしたアドベンチャー」になる予定です。基本的には3Dなのでキャラを自在に動かして、いろんな情報を集めたり、謎を解いたりしながら物語を進めていくものを考えています。
[tky_in_dev]
— Tokyo Stories Game (in dev.) (@tky_stories) July 29, 2022
01.background
開発過程をご紹介!
3D背景がピクセルアートになるまでをBreakdown映像にまとめました
Dev. progress sneak peek!
Here is a breakdown video of how a 3D background becomes a pixel art!#madewithunity #indiedev #tky_stories pic.twitter.com/mASV8HW6Yz
[tky_in_dev]
— Tokyo Stories Game (in dev.) (@tky_stories) July 30, 2022
02.character
キャラクターもいくつかの工程で出来ていきます
一番気合の入る箇所です
Characters are created through many stages.
We put a lot of effort into this part.#indiedev #pixelart #tky_stories pic.twitter.com/Ie3LzUKL0w
ーー試遊してみてアートスタイルにかなりのこだわりを感じました。どのようなコンセプトでああした街を作られていますか。
池田:私と寺島くんが考える“ノスタルジック”をキーワードにしています。
東京の作り方って最先端でキラキラしているイメージを打ち出すこともできますし、色々あると思うんですよね。でも、我々が本作で描きたいのは裏路地の打ち捨てられた雰囲気や、自販機の光から感じるノスタルジックさなんです。
本作ではそこを切り取ろうと考えて、今のアートスタイルに落ち着いています。ちなみにカメラも固定視点なので、その点でも少し古めかしさを感じるかもしれません。
ーー僕が本作で感じたのは、モトクロス斉藤さんやAPO+さんのような現代のピクセルアート作品や、『アンリアルライフ』といったインディータイトルです。彼らの影響はあるのでしょうか。
池田:正直めちゃくちゃ影響を受けています。『アンリアルライフ』も遊んでいますし、最近では『Stray』などもプレイしていて、「こういう路地裏を作りたかった……!」とすごく思っていました。おっしゃられたモトクロス斉藤さんやAPO+さんなど、世界でも有名なピクセルアーティストの方々の手法も参考にしています。
参考にしながらも、我々がやるのは「こういう綺麗さだよね」とか「こういう汚さだよね」みたいなところを出せるような絵作りを考えて進めています。
ーー『Tokyo Stories』に『rain』から引き継がれている面はありますか。
池田:ちょっとカメラシステムが似てるところがあるかな……と思ったりします。あの時はキャラが見えないゲームだったので、それに比べると作るのは簡単でよかったです(笑)。
甲斐:けど、漂ってくる雰囲気は通じるものがありますよね。
池田:やっぱり自分とアートディレクターの寺島くんの好きなところというか、温度感は10年経っても変わっていないね、みたいな。
ーー思い切った作りだと思ったのは、『Tokyo Stories』は歩くことに絞られていることです。多くのゲームプレイで情緒的な印象を生み出そうとするアクションですけど、退屈さにも通じかねない危うさもあるように思います。
池田:今回のデモ版を作っているときに、走れるようにもしたんですけど、走るという行為自体が楽しくなっちゃうっていう。端的にいうと裏路地を走り回るゲームになっちゃうんですね。
そうじゃなくて、自分たちが作りたいノスタルジックさって、こういう気持ちじゃないよねと。ノスタルジックな気持ちになるにはどうしたらいいかと考えると、走らなきゃいいんじゃないという結論にこの段階では至っています。
今回作ったシーンは街をさみしく、心細く歩くものなんです。ただ、今後の製品版では、もうちょっと激しめなシーンを作ったときには走れるようにすることもあるかもしれません。
今回のデモではけっこう歩くというのが上手くいったんじゃないかと思っています。歩きながら音楽を聴いて、テキストを読んでいく体験はあまり他にはないものかなと。
ーー海外のインディーゲームではウォーキングシミュレーターなど近いスタイルのジャンルがありますが、そうした前例などを意識していますか。
池田:海外タイトルだと違う系統のにはなっちゃうんですけど、『Limbo』とかが出た時「こういう作品を作っていいんだ!」と衝撃を受けましたね。
ーーなるほど、わかる気がします。
池田:ちょうどあの頃はインディーゲームの走りで「こういうゲームもあるんだ」と思って『rain』を作ったところもあるんです。
ーードリコムのこれまでのモバイルを中心としたゲーム事業とは真逆の印象があるプロジェクトですが、池田さんはどのような意識で開発を進めているのでしょうか。
池田:新しいことをやっているという自負もありますが、とにかく「自分たちが好きなものはここだよね」をブラさないようにやっているので、新しいことをやることが目的なのではなく、シンプルに自分たちが作りたいゲームを作ってユーザーから良い反応を得たいということを意識しています。
自分たちで「こういうゲームを作らなきゃいけないよね」という目標をしっかり決め、そこへ向かって議論しながら開発を進めています。
ーーPCでのリリースを考えているとのことですが、今後モバイルやコンソールでの展開も考えていますか。
池田:そうですね、現状だとPCとコンソールで出したいと考えています。PCの販売プラットフォームもそうですし、コンソールのプラットフォームもまだ確定していません。
まだまだモバイル以外ではノウハウが足りないという正直なところもあり(苦笑)、社内外で相談させてもらいながら方針を検討しています。
ーー逆に今回はスマホでのリリースを控え、買い切りのプラットフォームで勝負したいという意図も込められているのでは……?とも思いましたがいかがでしょうか。
池田:やめようっていう感じではないものの、やっぱり本作で自分たちが届けたいものっていうのが大画面で空間として浸れるものを届けるとか、PCだったら自分の部屋でヘッドホンをつけながら静かに遊ぶみたいな、そういう感じで遊んでもらいたいと考えているので、まずはPCとコンソールでのリリースを考えています。
スマホだと画面も小さいですし、今回満たしたい “浸る”って体験がちょっと難しいのかなと。ただ、絶対にやらないということはなく、良い形があればモバイルでのリリースも検討はしています。
ーー本作はクリアまでにどれくらいのプレイ時間を想定されていますか。
池田:現時点では「濃密な2時間か3時間」を計画しています。チームのメンバーと話している中でボリュームやリプレイ性を上げたほうがいいのではというアイデアも出てきてはいるのですが、決して潤沢にリソースがあるわけでもないので、いま我々が集中できるところってどこなんだろう? と考えて、濃密なワンプレイの密度を高めることに集中しよう、という方向性で進めています。
ただ、いまは並行してシナリオを作っており、シナリオ側でたとえば1週目はここを見せる、2週目はここを見せたほうが全体の体験としてよくなるといった議論も重ねています。お話の筋はちゃんと通っていて、各周回のプレイでどこの断片を見せるかというところでリプレイ性を高めるような仕様も検討中です。
ーー完成はいつ頃の予定でしょうか。
池田:2023年に完成させるべく開発を進めています。