【GDC 2013 Vol.95】「プレイヤー殺し」の男はアメリカで何を感じたか?『ラ・ムラーナ』楢村匠氏が見たGDC
『洞窟物語』の天谷大輔氏に続き、日本のインディーゲーム開発者でGDCスピーカー第二号となった『ラ・ムラーナ』の楢村匠氏。アクションアドベンチャーゲーム『ラ・ムラーナ』を世に送り出したNIGOROのリーダーです。GDC最終日の3月29日に、講演の感想やGDCの印象、ゲー
その他
その他
『洞窟物語』の天谷大輔氏に続き、日本のインディーゲーム開発者でGDCスピーカー第二号となった『ラ・ムラーナ』の楢村匠氏。アクションアドベンチャーゲーム『ラ・ムラーナ』を世に送り出したNIGOROのリーダーです。GDC最終日の3月29日に、講演の感想やGDCの印象、ゲー
この記事の感想は?




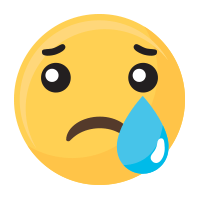

人気ニュースランキングや特集をお届け…メルマガ会員はこちら