
なお、ゲームは3週間で作られたとのこと。

新時代の到来であるとも言えそうですが、各国でレイオフの嵐が吹き荒れる今、クリエイターからはどのような反応があるのでしょうか。

声優・俳優と合成音声生成AI双方の落としどころを探ったハイブリッドAIライセンスが登場しました。
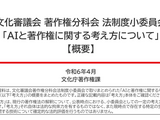
公表内容は現時点で検討された「考え方」であり、法的な拘束力を有するものではありません。

まだ課題は残されているものの、ゲーム開発に生成AIが本格導入される日が近づいたともいえそうです。

「TENCENT CLOUD DAY JAPAN 2024」より、基調講演とメディア合同インタビュー、さらに後日実施したメールインタビューの模様をお届けします。

OpenAIは15秒ほどの短い音声を元に、本人そっくりで、感情を込めたリアルな音声を生成できるAIモデル「Voice Engine」を発表しました。元音声と生成音声のサンプルがいくつか公開されています。

プレイヤーと開発者双方に価値のある生成AI技術活用を目指すとしています。

ベータ版が全てのAdobe Substance 3Dユーザーに順次公開されています。
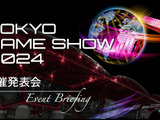
昨年開催のTGS2023と同程度の規模となる25万人の来場を見込んでいます。

周年イベント時に収益が大きく向上しています。

Adobeは2月4日、Creative Cloud個人版プランを3月5日から値上げすると発表しました。Creative Cloudの日本での値上げは2022年4月以来2年ぶり。

小規模デベロッパーの開発やユーザー生成コンテンツ、MODが進化するとの期待も寄せられています。

レイオフへの懸念、生成AIの是非、SNSの現状をどう見るかなど、さまざまな観点からゲーム業界の現状が浮き彫りになっています。

PCゲーム最大手がAIコンテンツの利用作品の受け入れを開始。

契約していない限り他のModの再利用などは不可能であり、独立した完全新作でなければならないという旨が記載されています。

米国政府はAIや機械学習に使われるGPUにつき、中国への輸出規制を強化しつつあります。その範囲は次第に拡大し、ついにNVIDIAの最新GPUであるRTX 4090にまで及びました。本来はゲーム用ではありますが、非常に高い演算能力を誇り、当然AI用途にも転用できるためです。

生成AIをゲーム開発に活用するサービスを展開するWitchpotは、生成AIをベースとするゲーム世界観・設定制作管理用ツール「Glimnote」の提供を開始したと発表しました。

東大発AIスタートアップのEQUESとセガが3Dモンスター生成AIを開発しました。

パートナーシップは複数年度にわたるとしています。