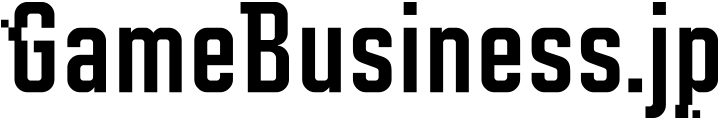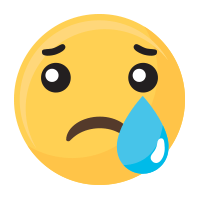|
| 講演会の様子 |
酒井氏は、『セガカラ』に携わり、新小田氏はプロデューサとして、ロッソ氏はディレクターとして『源平大戦絵巻』、『アレクサンドリア大戦絵巻』並びに『百鬼大戦絵巻』(以下、『大戦絵巻』シリーズ)を開発しました。
その中で、昨今隆盛を極めるこれら新鋭プラットフォームのために作品が如何に作られ、プロデュースされているのかについて伺う事が出来ました。ここではその模様を中心にお伝えしていきたいと思います。
■『セガカラ』で展開するユーザとの接点を高めるコンテンツプロモーション
『セガカラ』(AppStore)はセガが展開するカラオケサービスのブランドです。PC版と、iPhone版がありますが、酒井氏は、iPhone版を担当。ただし、「自分自身の経歴はゲーム業界ではかなり異色です」と分析します。
元々、ゲーム開発を希望して大手ゲーム開発スタジオに入社したそうですが、任されたのは世界初の通信カラオケシステム。その後、モバイル事業に関わった際も、着メロサービスに携わり、300万人強もの会員を抱える巨大サイトの開発運営をしていたとのこと。
『セガカラ』においては、産学連携で企画コンペを実施。映像学部生50名7チームによる様々なアイデアの中から、『セガカラ』の背景画に大学生による応援シーンを用いるという案を選抜。今年の春からは、7人の学生たちと共にプロジェクトを進行させているとのこと。正式名は「セガカラ×立命館チアフルキャンパスキャンペーン」。学生たちは、その期間、セガカラ公式アカウントの運営にも参加しつつ、同キャンペーン専門のFacebookページも開設。数ヶ月にわたって制作してきたキャンペーン用背景画の制作秘話が明らかにされました。
これらの企画は、定期的に酒井氏が進捗を確認しながら、必要に応じて社内調整をしつつ実現。酒井氏は「わたしは、3年生の皆さんと去年の10月から発表の審査や、打ち合わせを続けつつ、「『セガカラ』と学生さんとで何が出来るか」を考えながらここまでやってきました。これからはこのコラボレーションを成功させる様、頑張っていきます」とその意気込みを示しました。もともと大学生のレクレーションで欠かせないのがカラオケ。そのような意味で、ターゲットユーザそのものである大学生とともにプロモーション企画を考えていくというプロセスは、いまの学生のニーズを把握するうえでも意義がありそうです。
■『源平大戦絵巻』が『Samurai Bloodshow』になった理由とは?!
----
一方、講演前にいただいたプロフィールから圧倒されたのが『大戦絵巻』シリーズの開発者である、新小田夢童氏(以下、新小田プロデューサ)とデュラ★ロッソ氏(以下、デュラ氏)。新小田氏は、虚無僧、デュラ氏は、地獄の使者の衣装を身にまとうというその出立ちも特殊ですが、クリエイティブな仕事をしつつ、自らプロデュースやプロモーションにも関わっていくというのが『大戦絵巻』シリーズ開発チームのポリシーであるようです。
冒頭は、デュラ氏と新小田氏が『大戦絵巻』シリーズの開発秘話を披露。2011年6月2日にリリースされた『源平大戦絵巻』(以下、『源平』)を皮切りに、『アレクサンドリア大戦絵巻』(以下、『アレクサンドリア』)、『百鬼大戦絵巻』(以下、『百鬼』)と既に3作品がリリースされています。これらの作品における共通点は、プレイヤーが指揮官となり、複数カードで部隊を編成。iPadを絵巻物に見立て、自軍の大将に向かってくる敵を殲滅していくという点。グラフィックは、当時の絵巻物や、パピルスのデザインをそのままモチーフにし、まるで「動く絵巻物」といった感があるのがこのシリーズの特徴です。
2011年6月に発売された『源平』は、同年9月には『Samurai Bloodshow』として全世界に配信開始。現在、日本語、英語に加え、韓国語、中国語、フランス語、スペイン語等、全6カ国語で展開。これまで30万ダウンロードを突破したとのこと。また海外各国のゲームレビューサイトでもそのゲーム性が高く評価されているとのことです。
ここで、デュラ氏が海外向けタイトルの命名エピソードについて語りました。「Bloodshow」(血のショウ)とは、敵を倒すと血しぶきしたたる『大戦絵巻』シリーズとしては如何にも、といった響きですが、「きっかけは実は全然ちがう」とデュラ氏。「その当時、作り始めの頃はやっていたTVドラマ「Sex and the City」の主人公がCarrie Bradshawだと知ったとき、コレだっ!とひらめいたんです」(同氏)。
このように、推敲に推敲を重ね、考え倒すだけでなく、脱力して考えたときにいいアイデアが出る場合もあるとし、アイデアが如何に多様な形で出てくるのかを示しました。
ゲームを開発するにあたり、考えたのが日本としての強みを生かす事。そこで、他国でも扱われるであろうSFやファンタジーなどではなく、日本の歴史をゲームの題材にしたとのこと。
更に音楽にもこだわったとデュラ氏。日本の代表的な和楽器である琵琶を使用したのに加え、テクノを入れるなどして、ネオジャポニズムをテーマとして作ったとのこと。この音楽が好評で、iTune Music Storeで楽曲を配信したところ、全サントラアルバム部門ランキングで第1位を獲得しています。
一方、2作目である『アレクサンドリア』では、世界二大文明である、エジプトと、ギリシャをぶつけたいという思いから開発したとデュラ氏。アレクサンドリアはこの二大文明の分岐点というところでタイトルも決定しました。また、『源平』の正当続編にあたる『百鬼』は、従来の源平というテーマに妖怪を大量に追加。これらの妖怪デザインは、「百鬼夜行絵巻」をベースに、歌河国芳や、河鍋暁斎などの妖怪絵師が描いた魑魅魍魎を取り入れているとのことです。
■ゲームバランスを洗練させ「脳汁が出る」体験を保証する
----
これらを踏まえて、語られたのがゲーム開発、プロデュースにおいて留意するべき点。デュラ氏によれば、ゲームの肝は「バランス調整」とのこと。具体的には、パラメータ調整、敵出現のタイミングを確定するエネミーセッティング、どれだけの時間で何が生成されるか、そして制限時間を決めるタイムコントロール、並びにリソースコントロールを指します。実際、企画書には訴求ポイントとして、グラフィックや、システムのギミック、著名な原作のゲーム化などが言及されるものの、これらはあくまでもゲームの「飾りでしか無い」とキッパリ。ゲームにおいては、パラメータ設定が確定されることでデジタルデータに「魂」が吹き込まれてはじめてデータがキャラクターへと生まれ変わるのだとしています。
この他にデュラ氏が言及したのが「脳汁」現象。これは、ゲームに夢中となり興奮してプレイし続けた結果、脳がシビれたような感覚を受けることを指すとデュラ氏。ゲームディレクターは開発中にゲームの優劣を判断する際、この体験の有無を面白さの指標とし、デザイン調整するとのことです。この体験無しにグラフィックの秀逸さのみを追求してしまうとプロジェクトは炎上するとデュラ氏。
同氏は、更に「脳汁が出る」現象を生み出しやすい体験として、「ギリギリで競り勝った時」、「絶対絶命の危機を脱した時」、「不利な状況から大逆転した時」、「すごい速度でタスク処理を要求された時」、「すごく速いものをコントロールする時」、「勝利への勝ち筋を脳内で思考錯誤している時」等を挙げ、これらを総じて「脳というコップの表面張力ギリギリまで負荷を与え、思考のクロック数をあげた状態」と表現。この現象を脳が「面白い」と錯覚するのだと持論を述べました。ゲーム開発者は人間のこの特性を利用する形で、ユーザーにとって高く評価されるゲームを開発できるのだと言います。
また、ユーザーの「脳汁」を引き出すには、難易度の強弱が重要とデュラ氏。今回の講座ではその点について『百鬼』を例に説明しました。同作は、各ステージごと「手ごわい」と「手ぬるい」モードがあり、双方とも敵の攻撃が10ウェーブで構成されています。普通に考えれば、ウェーブが上位に上がれば敵数も多くなると考えがちですが、「手ぬるい」モードでは、第四ウェーブまでは敵数も漸増するものの、第5ウェーブ目で一気に敵数を増やすのが重要とデュラ氏。第4ウェーブまでの間に、ユーザーに自信をつけさせておき、第5ウェーブで危機感を煽る事でスリルを感じさせるというわけです。第6ウェーブからはまた一気に敵の数を減らし、そこから改めて敵数を漸増させ、最終ウェーブでは同ステージ最多の敵を出現させているとのこと。「手ごわい」モードでもこのペースを早めながらも強弱は同様につけているということが明らかとなりました。
■自らの子供と思い、ゲームの認知度向上のためにあらゆる手をつくす
----
更に、汎用機向けゲームを展開するうえで重要なのがプロモーション。開発規模も予算も限られているプロジェクトのディレクター、プロデューサとして、自分たちは出来る限りの事を全てやってきたとデュラ氏。自らゲームをモチーフとしたキャラクターを演じることを皮切りに、主題歌も作曲。ギターも同僚の中でギターが出来る人にお願いし、自らビデオカメラを持って撮影、編集し、動画共有サイトにアップしています(新小田夢童、まさかのカラオケ界に殴り込みの巻)。
 |  |
| 自ら体を張ってプロモーション | |
「『大戦絵巻』シリーズは自分の子供。全部かわいい。どれ一つとして劣っているモノはないです」と自らの作品に対する思いを伝えつつ、「自分のエゴは無くし、如何にして「この子供たち」をアピールするべきかを常に考える事、このまま魂削ってもいいんだ、という意気込みでやる」ことがプロモーションでは重要と情熱的に語りました。
虚無僧を演じる新小田プロデューサも、ここまで自らの体を張って作品展開をする理由として、「ディレクターの頑張り」を挙げました。「隣で1週間も徹夜をしてモノ作りに励んでいる姿を見ていると、その思いに応えなければという気持ちが自ずとモチベーションになる」とのこと。また、キャラクターを演じ続ける事については、「仮面をかぶるという事に対してネガティブなイメージがありますが仮面をかぶるのは社会人として当たり前。だから仮面をかぶることはいいことだと思います。皆さんも、自分なりのスイッチを入れる方法を考えた方がいい。それが分かると、どんなに疲れていても気持ちを切り替える事が出来る。これを恥ずかしいとか中途半端にやっているほうが格好悪い。」とプロデューサとしての見識を示しました。
■ソーシャルメディア台頭の時代に必要とされるクリエイター像
今回は、セガでスマートフォン、タブレット端末向けゲームやコンテンツを開発している3名の方々による講演でしたが、それぞれ如何にコミュニティを意識しているかというのを改めて実感出来ました。また自身が開発したものを信じ、チームが持っているあらゆるリソースを活用して認知度を高めようとする3人にゲーム開発者としてのプロ意識を垣間見ることが出来ました。このように自らの声を積極的に受け手に発信していく事は、作り手と受け手の間の距離が比較的に狭まりつつあるソーシャルメディア台頭の時代には欠かせないのかもしれません。