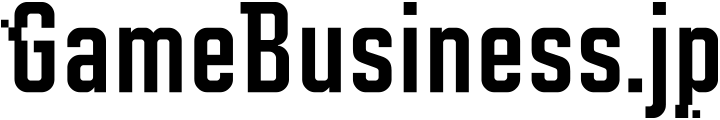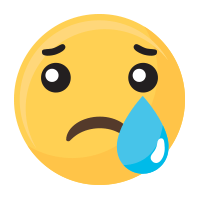そして、満を持して10月13日、PlayStation VRが発売されました。そのような事もあり、今年は様々なイベントでVRサービスの展示が数多くされていました。そのような中から、本稿では『エニグマスフィア~透明球の謎』(以下、『エニグマスフィア』)開発中の株式会社よむネコの代表取締役社長の新清士氏と、プログラマーの田端秀輝氏にその経緯を伺ってきました。『エニグマスフィア~透明球の謎』とは、プレイヤーはスーパーエージェントとなってアンドロイドを操作し、悪の帝国が設置した惑星破壊兵器内に潜入。設置された制御装置の「スフィア(透明球)」を制限時間内に全て破壊して地球を救うことを目的としたパズル型VR脱出ゲームです。では、インタビューの全容をお伝えしましょう。
Oculus Touchで受けた衝撃を可能な限りゲームデザインで表現しようと開発を決意
――まず、開発のきっかけを教えてください。
新清士氏(以下、新):2015年のTGSのときにOculus Touchを体験し、VR空間でモノを持って遊ぶという感覚に、いままのゲームにない、「凄い何か」を感じました。それ以降は、この感覚を如何に活かせるかということをずっと考えていたんです。あと当時、脱出ゲームを経験したり、スマホ版の脱出ゲームを開発していたりしたのですが、その中で、VRと脱出ゲームというのは非常に融和性があるなと確信したのが、VR脱出ゲームとしてコンテンツを開発するに至ったきっかけです。

――開発当初の企画はどのようなものだったのでしょうか?
新氏:初期でつくっていたバージョンは所謂「脱出ゲーム」でのユーザー体験を移植しようと考えていました。ただ、実際つくってみると、「脱出ゲーム」をそのまま再現するだけでは、思っていたほど面白くないということに気づきました。まず、ユーザーテストを繰り返す中で、VR内で出来ることと出来ないことに、ユーザー間に大きな差が出てくることが分かったんです。VRが初めてで且つ普段ゲームをあまりやらない人にテストしてもらうと移動すら出来ないということが分かります。
あと、コントローラでの移動をユーザーに強いると絶対に酔うんですよね。本作も、当初は炎からの脱出を想定しており、炎がユーザーを襲うというシーンがあって、VRでは本当に恐怖すら感じられたのですが、これは移動することで初めて感じる恐怖だったので、VR酔いがあるとそれらを感じられない。結局、VR酔いの問題が解決できずにあきらめざるを得ませんでした。
その頃、たまたまGame Developers Conferenceに行ったときに得た、ワープ概念を、実装してみると、VR酔いの問題を解決できたんです。その後、テストを繰り返して、今に至っています。この他に、通常の脱出ゲームのしくみそのものを仕組んでいたんですが、VRゲーム内ではそれが機能しなかったんです。思ったより解けなかったひとが続出して。結局、リアルな脱出ゲームのデザインをそのまま移植するだけでは面白くないという結論になりました。ただ、その段階ではどうすれば面白くなるかは分かりませんでした。これで超苦しんでいたのが今年の4月ごろです。
――いまのゲームとは全く違う感じですが、デザインの変更はいつごろからしたのでしょうか?またその理由は?
新氏:このゲームはVR Startupのプロジェクトとして出資を受けているので、出資受け入れ期間全6か月の中間にあたる3か月目に中間報告が入ったのですが、そのときの内覧会でかなり厳しい指摘を受けたんです。このままではダメだという空気でした。そこでとにかくユーザーテストを続けました。その中で「モノを壊す」という行為が面白いことに気がつきました。
VR空間なりの「リアル」を体験させることが出来るか否かがVRゲームの優劣を決定づける

――筆者もスフィアが割れたときは不思議な爽快感を感じました。
新氏:結局分かってきたのはVR空間というのはその空間での「リアル」が存在するということ。これを最初から理解してコンテンツを開発しているひとはすくないと思います。そういった意味で、いまの段階でこのことに気がつけたのはよかったと思いました。
――VR空間での「リアル」とは?
新氏:VRのなかで表現できるリアリティというのがあって、それをどうユーザーに納得させるためのきっかけをつくり、その「Feeling」を如何につくっていくのか、という点です。これが分かってから、ゲームをデザインするうえでそれをずっと追及していきました。それが「スフィア」であったり、透明球を破壊するというコンセプトです。現実世界で、ガラスとかは壊せないですよね?なので、壊す感覚が面白いんです。スフィアを導入した当初、壊れたガラスを床に飛び散ったままにしておいたのですが、ユーザーの中には破片を掃除する人が出始めたんです。女性プレイヤーなど特に(笑)。
制限時間内にクリアしなければならないので、掃除している時間なんか本当は無いはずなのですが(笑)。ゲームを進めるのを忘れて掃除をするという…こでコレだっ!と思いました。何か新しい感覚がここにはあるんだと。それもゲーマーと非ゲーマーの両方がそういった体験を面白いと言いだしたのは新鮮でした。そこでゲームデザインをそちらのほうに振り切ろうと決めました。これが見えてきたのが5月末ですね。そこからやっとゲームステージの作り込みが出来るようになりました。テストプレイした皆さんが面白いと言いだしてきたのもこの時期です。ちなみに、スフィアが砕けたあとの断片はいまでは自動的に消滅するように設定を変えました(笑)。
物語世界の構築が、プレイの持続性を促す

――世界観はいつごろから作り込んでいったのでしょうか?
新氏:物語は6月ごろのバージョンには入っていませんでした。物語を入れることにしたのはバンダイナムコ様が運営する「なぞともカフェ」へ出展するにあたって入れたものです。あの場所ではすべての体験が765秒ぐらいで終わらなければならないというルールがあります。つまり10分強ですね。なので、単純にパズルが並んでいるだけでは面白いと思ってもらえません。そこでユーザーが遊びを続けるためのモチベーションを維持する何かが必要ということで、バンダイナムコ様からも物語を導入することについて提案を受けたんです。「ものすごく簡単なものでも構わない」とのことで。そこで以前からお付き合いのあった、謎解きゲームのシナリオライターさんにお願いして、「帝国」、「地球が破壊される」、そして「装置を止めることの必然性」といったストーリー要素を入れていきました。
――ユーザーの反応は?
新氏:ゲーム世界へなんの抵抗もなく入っていきました。とにかく何かしなくちゃいけないんだと。誰ひとりとして疑問を感じなかったんです。つまり、没入度が上がったのだと思います。やはり、急いで解かなくちゃ…とか、クリアしなければという気持ちが凄く増したと思います。なので、物語は入れたほうがいいですね。ただ、物語を長々と説明すると、それはそれでユーザーは面倒くさいと感じてしまいます。だから出来るだけシンプルに。例えば『アングリーバード』なんかいい例ですよね。あれは、ストーリーはあってないようなものですよね。なんで怒った鳥が飛ばなければならないのか?まあ、卵を盗まれたから取り返さなくちゃいけないんだろうなとユーザーは勝手に想像するわけですが…ストーリーはあまり意識しないのですが、なんとなく卵を取り返さなくちゃという理由にはなっているんですよね。
つまり、ストーリーはゲームプレイをするうえでの「フック」にさえなればいいんです。ということで、僕らではそういったストーリーを入れて、せっかく物語を入れるのならば、ムービーも入れようと決め、簡単なものを追加したという感じです。Unreal Engineで宇宙船や爆発シーンをつくり、それを映像化したものをVR空間のブリーフィングで投影するという手法を採りました。実はあの、汚れた映像の雰囲気はiPhoneを使って作ったんです(笑)。最後の爆発シーンは、9月上旬に作りました(笑)。
タイトルは世界市場を意識し日本、海外双方で記憶になるものを意識
――現状はいかがでしょうか?
新氏:現在、ゲームステージを更に作り込んでます。ゲームとしてはシングルプレイも可能なのですが、脱出ゲームはマルチでやったほうが楽しいので、マルチプレイを推奨しています。ですので、イベントなどに出展する場合は、マルチプレイのデモをおこなっています。
――海外市場も意識して開発したのでしょうか?
新氏:最初から英語対応にしています。これはマーケット全体がまだ小さいからです。まず、アメリカに売らないとマーケットは無いので。ただ、欧米のプレイヤーが理解しやすいようにゲームデザインを工夫するという段階には入っていません。欧米のプレイ感覚は実際にプレイしてもらわないと分からないので。でもタイトルにはこだわりました。英語が母国語の人に相談して、タイトルを見てすぐにアメリカ人でもそのゲーム内容がイメージ出来るものにしました。「ミステリアス」で且つ「一度聞いたら覚えられる」というタイトルです。同時に日本人でも覚えられるタイトルを考え続けて行着いたのが現在のタイトル名なんです。

このような経緯で開発がほぼ終盤に移りつつある『エニグマスフィア』。Oculus Touchの発売にあわせてリリースされることも決定しており、新機能を試したいというユーザーにとっても、新たにRiftやHTC Viveの購入を検討している人にとっても最適なゲーム体験を約束できる一作としての期待が高まる。すくなくともそれだけの研究を積み重ねて今のゲームデザインに至っているという点はインタビューからも確認出来た。これは、自然に自身の興味が深まった分野に素早くネットワークを培き、その本質を理解しようと総力を尽くすジャーナリストとしての新氏の素養が本プロジェクト開発において存分に発揮された瞬間とも言える。だが同時に、多数の仕様変更が短期間に行われてきたのも事実だ。その点について、プログラマーの田端秀輝氏に開発状況を伺ってみた。「マスターアップ直前に、レベルデザインを自ら担当している社長がこれを入れてくれと…」。新氏自らの前著『侍はこうして作られた』で記された開発現場の修羅場が正に目の前にあるということを感じつつも、従来の枠組みに囚われない作品の登場に期待を抑えられない瞬間となった。