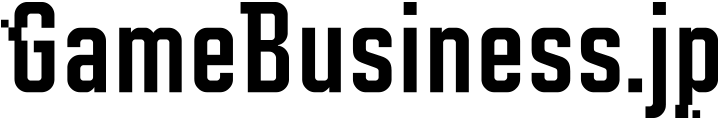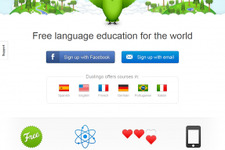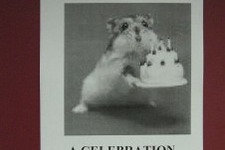「MINI Coupéハンティング大作戦」とは?
日本でのMINIクーペ一般初公開を記念したBMW社のキャンペーン。スマートフォンアプリの地図上に表示される「バーチャルMINI Coupé」を奪い合うGPS連動型の一般参加型のゲームです。
東京モーターショー(12/3〜11)が開催している9日間、ゲーム参加者が「バーチャルMINI Coupé」保有者の50M以内に近づくと、MINIクーペの保有権を奪い取れる仕組みになっています。そして終了日の13時に「バーチャルMINI Coupé」を保有していた人には、MINIクーペの実車が贈られます。また、開催期間中、毎日20時に「バーチャルMINI Coupé」を保有していた人には、MINIアドベンチャー賞がプレゼントされます(ゲーム対象範囲は東京23区内)。
BMW 日本法人によると、12月2日までの間に既に5000人がアプリをダウンロードし、ゲームへの参加表明を行なっているとのこと。日本での例は少ないですが、リアルとバーチャルが融合したキャンペーンは注目分野です(海外の類似キャンペーンについてはこちらの記事が参考になります)。
下記、このキャンペーンがどの様にGamification要素を用いてユーザーの心を掴んでいるのかを考察しながらのレポートになります。
昨年を上回る来場者数を誇る、第42回東京モーターショー。

お、何やら「MINI Coupéハンティング大作戦」からこんなメッセージが。

こうした一工夫がゲームへのわくわく感を高めてくれます。
さてMINIクーペのブースに到着しました。そろそろゲーム開始…とアプリを開くと、既に誰かがMINIクーペを保有しているようです。早速追いかけましょう!


さっそく保有者が早速会場から出た模様。もちろん追いかけます!人の姿ではなく、GPSの座標を追うスマートフォン鬼ごっこ。長くなるので割愛しますが、追跡の様子はこんな感じです(結構走りました)。

一瞬ですが、MINIクーペの保有に成功!そして一瞬で奪われました…。

と、本気で楽しんでしまいましたが、この企画がどういう仕掛けで筆者を楽しませてくれたのかを考察したいと思います。
「スマートフォン鬼ごっこはなぜ人を夢中にさせることができるのか?」
1.現状の可視化 (地図により一目で把握できる)
2.目標設定 (達成できる小目標や報酬の存在)
3.リアルとの連動 (参加者の緊張感と参加意識の向上)
1.現状を一目で把握できる
このゲーム、地図上で「自分が目標物(MINIクーペ)にどの程度近づいているのか?」が一目でわかります。そのため、次のアクションを考えることができます。例えば、自分と目標物が案外近くにいると分かると「走ってみようか」という気になりますし、距離が遠いときは「保有者はどのルートを辿るだろう?どうすれば近づけるだろう?」と地図を眺めながら作戦を立てることができます。
(実際筆者は保有者との距離が遠いと判明したとき、「駅に先回りして待ち伏せ」作戦をとりました。結果、ハンティング成功!です。)
また、そうしたアクションの結果、目標物にどの程度近づけたか、近づけなかったとしたら次はどうすれば良いかと考え次の手を打つことができます(PDCAを回せる、というイメージです)。目標に対し自分は今どういう状況にあるのかが分かると、次の手を考える気になり、ゲームへのモチベーションがわいてきます。地図は目標物と自分の位置が一目でわかるので、現状の可視化に適していると言えます。
(もちろんあまりに目標物との距離が遠いときは「あきらめる」という選択肢もユーザーに残されています。現在進行形のこのゲーム、筆者が確認したところ、現在の保有者はとんでもない場所にいました…。

このように参加者はゲーム開催中、現在の状況をいつでも確認でき、「もし自分の近くに目標物がきたら追いかける」ことができるためゲーム参加の敷居が低いといえます。)
2.ユーザーの離脱を防ぐ目標設定

図のように、ユーザーの最終目的(MINIクーペの所有)を果たすにはいくつかの目標に細分化して考えることができます。MINIクーペを所有するためには終了時刻にMINIクーペを保有する必要があり、そのためには他の参加者からMINIクーペを奪い取る必要があり…という具合です。
「さすがに車は手に入らないだろう…」と思って始めた筆者でしたが、小目標である「MINIクーペの奪取」に成功しただけで、意外と最終ゴールのMINIクーペが手に入るかも?!と興奮し、今なおMINIクーペの行方をチェックしてしまっています。このように達成可能な小目標があると、次の目標にも挑戦しようというモチベーションが生まれます。
また今回は毎日20時に「バーチャルMINI Coupé」を保有していた人に副賞が与えられる仕組みがあり、この副賞狙いで参加するユーザーも多そうです。このような報酬の存在も参加者ものモチベーション維持に効果的と言えます。
3.リアル連動ゆえの緊張感がゲームをもりあげる
最後は筆者の感想になりますが、この企画がやっていて単純に面白かったのは、リアルとバーチャルが融合したゲームだったからだと感じています。
このゲームは現実と連動しているために制限や拘束が生じ、それらがゲームの緊張感を増してくれます。例えば個人の身体能力(走る速度の個人差)はもちろん、ゲーム中の移動範囲も制限されています(東京23区外に出るとゲーム無効)。またゲーム参加中はGPSで自分の居場所が他の参加者に知られてしまいます。このように参加者に現実的におこる拘束が緊張感を生み、ゲームへの参加意識を高めてくれます。
オンラインのみで完結するものであれば、緊張感やそこから生まれる参加意識というのは感じにくいのではないでしょうか。