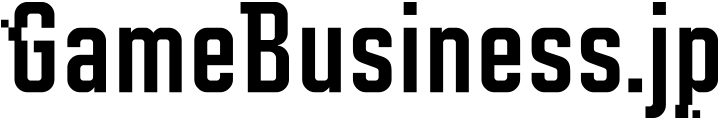2024年8月30日に西遊記ACT『黒神話:悟空』が発売されました。中国神話を元にしたこのゲームは、その世界観と美麗なグラフィック、爽快感あふれるアクションと高難易度で歯ごたえのあるボス戦などが絶賛され、圧倒的な高評価を受けています。2025年には総販売本数が2,500万本を突破したことも記憶に新しい出来事です。
同じく古代中国を舞台にした『明末:ウツロノハネ』は、PC/コンソール向けに2025年7月24日にリリースされました。
明朝末期という時代設定、“羽化病”なる奇病がはびこる戦乱の世界という舞台設定、凛と美しい女性主人公、そして迫力満点(に見えた)戦闘アクション…『黒神話』の成功を受け、ゲーマーからの視線は熱く発売前から期待が寄せられており、もちろん筆者もその一人でした。
するとどうでしょう。発売当初から、Steam版の最大同時接続数が11万人を超える驚異的なロケットスタートを見せ好調かと思いきや、レビューステータスは「やや不評」状態。そして執筆時点(7月27日)においても、レビュー数はすでに2万件に達しているにもかかわらず、未だ「やや不評」どまりです。さらにメタスコアでもPC版が76点、PS5版が75点というなんとも冴えない結果に。『悟空』のメタスコアが82点だったので、なおさら低く感じます。
名実ともに大成功をおさめた『黒神話:悟空』の一方で、早くも躓き暗雲立ち込める『明末:ウツロノハネ』。この対照的な2作品の明暗を分けたものはいったい何なのか?そしてゲーム業界において存在感が増している「中国産ソウルライクアクションゲーム」の魅力とは?両作のプレイを通して筆者が感じたその現在地と今後の展望について迫りたいと思います。
※記事制作にあたり、505 Gamesより『明末:ウツロノハネ』ゲームコードの提供を受けています。
◆『黒神話:悟空』に見る「中国産アクションゲーム」の魅力

1.“中国初のAAAゲーム”『黒神話:悟空』の成功
中国を拠点にしたゲームスタジオは数多く、『原神』『ゼンレスゾーンゼロ』でお馴染みのHoYoverseや、惜しくもサービス終了してしまった『SYNCED』を手がけたNExT Studioなど、さまざま規模のデベロッパーが活躍しています。
そもそも中国における「国産ゲーム」と言えば、モバイルプラットフォーム向けの基本プレイ無料/アイテム課金型のタイトルの開発が盛んです。そういった背景もあり、『勝利の女神: NIKKE』のテンセント、『荒野行動』『IdentityⅤ 第五人格』のNetEase、先述のHoYoverse、『ブルーアーカイブ』のYostarなど、全世界のモバイルゲームパブリッシャー売上ランキングにおいて上位を占めています。
しかし、逆に言えば世界のコンソール市場において「中国産ゲーム」の存在感は無いに等しく、それこそが中国国内のゲーム業界では非常に大きな課題として立ちはだかる壁でした。
そんな中、広東省深センで「Game Science(ゲームサイエンス)」という独立系スタジオが、2014年に馮驥(フェン・ジー)によって設立されました。当初は従業員6人ほどの小規模な開発体制でしたが、何度も巨額の投資を受けつつ着実に開発規模を拡大し、ついには2020年に『黒神話:悟空』の発表へと至ります。

コンソール向けのアクションRPGというジャンル自体、Game Scienceにとっては初めての舞台でした。しかし蓋を開けてみると、発売からわずか3日で販売本数は1,000万本に到達し、Steamにおけるプレイヤーの最大同接数はピーク時に220万人を超え歴代2位という快挙を達成するなど、驚異的な成功をおさめました。
その後も高評価を重ねていき、TGA2024では「ベストアクションゲーム」。Steamアワード2024では「ゲーム・オブ・ザ・イヤー」を獲得。名実ともに『黒神話:悟空』は「中国史上初のAAAゲーム」として功績を残したのです。
2.圧倒的な品質と中国文化の融合による独自性

大成功をおさめた『黒神話:悟空』ですが、その魅力とはいったい何なのでしょうか。それは皆さんご存知の通り、圧倒的なビジュアル、没入感のある世界観、そして爽快感抜群のアクションにあります。
とくに筆者が感じたのは、従来のソウルライクと比較して遊びやすい難易度設定になっているため、アクションゲーム初心者でも楽しめること、如意棒を駆使したアクションや、法術を組み合わせた「悟空」になりきれる楽しさ、そしてUnreal Engine 5による美麗なグラフィックと、「西遊記」をベースに中国の仏教・道教を題材にした奥深い物語の融合は、「中国産アクションゲーム」にしかない魅力的な要素です。
つまり、中国国内初のAAAゲームでありながら、確かな技術力による圧倒的なゲーム品質と完成度が世界中のプレイヤーから評価されたのです。
◆『明末:ウツロノハネ』に見る中国産ソウルライクの現在地

1.良い点と悪い点
先述したように、Steamレビューにおいて厳しい批判や意見が多く見られる『明末:ウツロノハネ』ですが、筆者が実際にプレイしてみた正直な感想は、「欠点は多くあるものの、遊べない作品ではない」というものでした。
まず本作の良い点について挙げると、没入感のある世界観、欠点はあるが独特なソウルライクアクション、迫力のあるボス戦、日本語ボイス対応などが挙げられます。特に、明代末期の蜀を舞台にした広大なオープンワールドは、当時の中国を忠実に再現しており、高品質なグラフィックも相まって惹きつけられました。
また、従来のソウルライクを踏襲した戦闘システムに加え、ジャスト回避などを成功させるとダメージを強化できる独自の「須羽」システムが加わることで、戦闘の爽快感がかなり味わえました。

一方で、最適化不足やゲームバランス、UI/UXなどに課題があり改善が必要な点がいくつか見られます。特に、動作の重さや敵の硬さは、多くの不満がレビューでも散見されています。
確かに、それらの欠点については筆者も感じました。とりわけ起動時のシェーダーコンパイルやゲーム設定の確認などでロード時間が長かったり、回避行動がスムーズでなくもっさり感が原因で敵の攻撃を避けるのが難しくソウルライクの醍醐味が損なわれていたり、ボス戦は迫力があるものの苛烈で難易度が高すぎたり、といった点が挙げられます。

2.現状と課題
この2点から中国産ソウルライクの「現在地」が見えてきます。壮麗なグラフィックや女性主人公の美しいキャラクターデザインなど、ゲームとしての「ガワ」は素晴らしい出来ですが、プレイヤーを不快にするためだけの理不尽な敵の配置であったり、把握しずらいだけのマップデザインであったりと、肝心の「ソウルライク」部分の作り込みが雑で完成度が低いのが現状です。
この賛否分かれる評価を覆すには、さらなるアップデートや早急な改善が課題と言えます。とはいえ、全く遊べないことはないし、むしろ素材としては悪くないので非常に惜しいゲームだと思います。
◆今後の「中国産ソウルライクアクション」に期待すること

『SEKIRO』ライクから武侠オープンワールドまで…広がる多様性
こうして良くも悪くもゲーム業界において存在感が増しているわけですが、2025年以降もAAA級の中国産アクションゲームのリリースが多く控えています。どういった作品があるのかいくつかご紹介しましょう。
まず最初は、PS5/PS4向けに発表された『百面千相』です。プレイヤーは、中国感たっぷりの美麗で広大なオープンワールドを舞台に、「百面先師」として様々な信念を持つ人々に出会い、その信念を体現した「仮面」を集める壮大な旅に出ることになります。
特徴的なのは、『SEKIRO』を彷彿とさせる本格的な剣戟アクションです。予告編でも確認できるように、パリィを使ったハイテンポな近接戦闘と中国風の体術を組み合わせたダイナミックなアクションが楽しめそうです。現時点で発売日は未定ですが、今後の動向に注目が集まります。
次は『Phantom Blade Zero』という作品。本作は、香港を拠点にするS-GameがPC/PS5向けに開発中のアクションゲームです。プレイヤーはエリートアサシン・Soulとして、66日という限られた時間の中で黒幕への復讐を目指します。
最大の特徴は、中国拳法やオカルト、スチームパンクを彷彿とさせる複雑な機械などをモチーフに描かれる「カンフー・パンク」と呼ばれる世界観で繰り広げるダイナミックな"武侠アクション”です。

数々のアクション映画を制作した谷垣健治氏をスーパーバイザーに迎え、徹底的にリアルな動きにこだわっており、剣術から体術、そして超人的な移動術を細部まで滑らかなアニメーションで再現されています。そして、往年のカンフー映画を取り入れた映画的体験は、ソウルライクという既存の枠を超えた「武侠アクション」という独自のアイデンティティを獲得しているとのことです。
そして最後は、『風燕伝: Where Winds Meet』。本作は、NetEase Gamesが手がける「基本無料」のオープンワールド武侠アクションゲームです。
10世紀の中国を舞台に、権力闘争と陰謀が渦巻く乱世の中、若き剣客が自らの運命を切り開いていくさまを描いています。剣、槍、双刀などの剣術に加え、豪快な接近戦などソウルライクをベースにした激しい戦闘、時間や天候によって変化する美麗なグラフィックと多彩なロケーション、ソロでも最大4人での協力プレイもできるゲームモード、そしてやりごたえ十分な150時間を超える豊富なやり込み要素など、無料プレイとは思えないほどの充実した作品になるとのことです。
このように「中国産ソウルライクアクション」というジャンルは、既存のソウルライクの枠を超えた多様性と広がりを見せつつあります。今後は『黒神話:悟空』と『明末:ウツロノハネ』が作り上げた土台をベースに、中国文化を取り入れたアイデンティティと「オリジナル性」の確立、そしてさらなる圧倒的な描写と壮大なスケール感の作品の登場が期待できそうです。