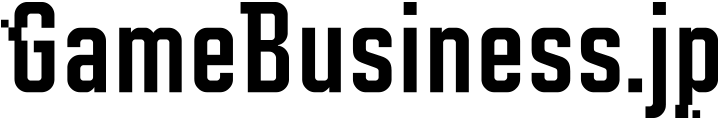はじめに井口氏より、VRにおけるゲームデザインで最も重要なことは「快適な体験をつくること」だと説明がありました。いわゆる「VR酔い」を生じさせないことが前提となると言います。
そのためにまずは「題材の選定」を慎重に行う必要があると言います。たとえば機体を主観で操縦し、急旋回・急加速をしながら飛び回るゲームは酔い対策の観点ではかなり難易度が高いそうです。また既存ゲームの移植では酔いへの配慮がなされていないため注意が必要だとアドバイスしました。
では、具体的にどのような対策が必要なのでしょうか。井口氏はまずはじめに「フレームレートを落とさない」ことを挙げました。Oculusのモデルでもそのあたり技術的な対策がなされており、Oculus Riftでは「90fps」、Gear VRでは「60fps」を下回らないように徹底されているそうです。
次にキーワードとして「ベクション(視覚誘導性自己運動感覚)」をあげました。たとえば電車に乗っているとき、隣の電車が動き出すと自分の電車が動いているように錯覚してしまうあの感覚です。VRを初めて体感する人はこのベクションに驚く人が多いそうです。
ベクションを発生させないために、「カメラの主導権をプレイヤーから奪わない」ことがポイントになると言います。ゲーム中、ロード画面やカットシーンなどあらゆる場面でカメラを強制的に動かすべきではないとして、プレイヤーの動きと連動してカメラを動かすべきだとアドバイス。酔い対策はもちろん、それがそれが没入感につながるそうです。
とはいえ、演出の都合上、どうしてもカメラを動かさないといけない場面が生じてしまいます。そんなときはどう対処すればいいのでしょうか。井口氏は酔いの発生度を以下のようにまとめました。
-停止<前<横・後ろ<斜め上<旋回
-低速運動<高速移動
-壁や地面が遠い<近い
-等速運動<加速・減速
-直線運動<曲線運動
-動きの軌道が事前にわかる<わからない
これによると、カメラを動かす場合は、なるべく前に等速直線運動で行うほうがいいことが分かります。また移動の際、加速・減速はベクションを発生させやすく、本来であれば不自然ではありますが、瞬間的にトップスピードまで上げるほうが良いそうです。
またゲームデザインを特徴づけるものとして「カメラ視点」があります。VRはプレイヤーがヘッドマウントを装着することもあり「主観」のイメージが強いですが、井口氏によると主観は必須ではないと言います。むしろ酔い対策としては、第三者視点のほうがつくりやすいと言います。
第三者視点の場合、ポイントとなるのは、「キャラクターを中央固定にせず動きに遊びを持たせること」「カメラポジションを引き気味にすること」だとアドバイス。
一方、主観視点の場合、従来のようなFPS操作をそのまま当てはめると極めて酔いやすくなり、とくに「旋回」がネックとなるそうです。
主観視点のシューティングゲーム『VE: Valkyrie』を例に挙げ対策が紹介されました。

このゲームは、主観ではありますが画面全体がコクピット画面で囲まれているため、周囲が動いても体が固定されている感覚が強くあります。これにより酔いが発生しにくくなっています。
続いて、VRコンテンツにおける「UI」について言及がありました。従来のゲームではよく画面端にパラメーターなどの情報が設置されますが、VRでは非常に見えづらく、また固定化されていることに違和感を覚えてしまうそうです。このあたり注意が必要だとアドバイスしました。
最後にまとめとして「『快適な体験』を出発点として考えるべき」だと強調しました。さらにVRゲームデザインはまだ発展途上であり、必ず実装してテストを行うべきだと語りました。とくに開発者自身は酔いに慣れてしまいがちなので、多くのテスターに協力をあおぐべきだそうです。
また今回のセッションで語られたノウハウは、同社作成の「ベストプラクティスガイド」でまとめられています。ぜひ参考にしてください。