現代演劇から考えるゲームの物語性・・・新清士「人とインタラクティブの間」 第1回
日本経済新聞IT Plusで「新清士のゲームスクランブル」を連載させて頂いている。その時々にゲーム産業内で起きている時事ネタを解説する主旨のコラムだ。
その他
その他
日本経済新聞IT Plusで「新清士のゲームスクランブル」を連載させて頂いている。その時々にゲーム産業内で起きている時事ネタを解説する主旨のコラムだ。
この記事の感想は?




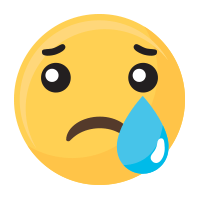

人気ニュースランキングや特集をお届け…メルマガ会員はこちら