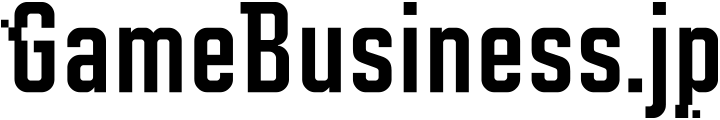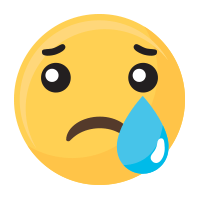CEDEC 2015で登壇したレベルファイブ代表の日野晃博氏は、基調講演「妖怪ウォッチ ゲーム・アニメ・映画・漫画・玩具 ~各界クリエイター共同戦線~」を、このひとことで締めくくりました。それは日野氏が業界外のクリエイターと、コンテンツの「共同制作」を続けてきた9年間を集約する言葉でした。
ゲームソフトシリーズ累計出荷本数900万本(DL版含む)を達成し、市場規模は2200億円ともいわれる『妖怪ウォッチ』。ヒットの理由には「妖怪メダル」を中核とした、ゲーム・アニメ・玩具・音楽・出版業界など、さまざまなメディアを巻き込んだ「クロスメディア戦略」にあると分析されています。
しかし、どのような構想も実現できなければ「絵に描いた餅」にすぎません。そして日野氏はこれが一朝一夕にできあがってきたものではなく、2007年に第一作が発売された『レイトン教授』シリーズから続く、異業種のクリエイターとの「モノ作り」の集大成だと説明しました。そこには互いのプライドをかけた、さまざまなバトル=魂のやりとりがありました。
■アニメ業界
レベルファイブとアニメ業界の関係は『レイトン教授と不思議な町』のゲーム内ムービーの制作から始まりました。「ニンテンドーDSの小さな画面で、映画なみのクオリティの映像を映し出す」ことに成功したことで手応えを得た日野氏は、続く『イナズマイレブン』シリーズでより深いコラボレーションを志向します。すなわちゲーム側からアニメ側に映像を発注するだけでなく、両者のクリエイターが一緒になって設定や脚本を考えるなど、新しい作品を一緒になって生み出そうとしたのです。
しかし、ここで両者の相違が大きく出ました。おもしろければ「何でもあり」で、奇抜で斬新なアイディアを歓迎するゲーム業界と、実写映像という先輩が存在し、世界観やキャラクター設定を重視するアニメ業界の溝は、思った以上に大きかったのです。これはプレイヤーが主人公となって操作できるゲームと、視聴者が観客となる映像という、メディアの違いだともいえるでしょう。
日野氏は「ゲームとアニメを両方おもしろくするための話し合いがここから始まった。これがあったから、『妖怪ウォッチ』における全コンテンツを通した作品のディレクションが生まれていった」と振り返りました。そして「ゲームとアニメは思った以上に違う。そのため早い段階から話し合いを密接にして、お互いに同志になるべし」と教訓を語りました。
■漫画家・出版業界
コロコロコミック編集部をはじめ、小学館との付き合いが深いレベルファイブ。しかし「漫画家は先生と言われるが、これまで異業種のクリエイターと対等につきあってきたため、この呼称に違和感があった」・・・日野氏は出版業界の慣習に対して、このように語りました。
もちろん集団制作が基本のゲームと、アシスタントを使うとはいえ、基本的には一人の漫画家がすべてを作り出す漫画では、コンテンツの創造プロセスが異なります。また、漫画独自の設定やエピソードを加味しなければ、作品の魅力が半減してしまうのも事実です。しかし、だからといって完全に作品作りを漫画家に一任してしまうと、クロスメディアが活性化しないと言います。
ポイントは漫画としてのオリジナリティと、メディア連携のバランスをとることで、『妖怪ウォッチ』でもいまだに意見がぶつかることがあるとのこと。「漫画家は『先生』ではない。ものづくりの仲間だ」と語りました。
■玩具メーカー
「子ども向けのコンテンツでは玩具との連携が作品世界にリアリティを与える上で非常に重要」日野氏はこのように切り出しました。
もっとも、そのためにはゲームの企画段階からどのように連携させるか、深く考える必要があります。実際に『イナズマイレブン』では「サッカー」という題材で人間というキャラクターが商材の為、みずから商品展開を狭めてしまったきらいがありました。実際に商材によって売れ行きが異なるなどの現象もみられました。
そこで、続く『ダンボール戦機』では「作品世界と同じアイテムを玩具として登場させる」ことをポイントに、「手のひらサイズのロボットで戦う」という基本設定を最初に作り上げました。これには日野氏が子どもの頃に好きだった『ミクロマン』などの影響があるといいます。
その結果、プラモデル版『ダンボール戦機』はゲームとの相乗効果を活かして、大ヒットを記録。第一作ではゲームにプラモデルをバンドルする斬新なパッケージで話題を集めました。「玩具はただの関連グッズではなく、作品に魅力を与える大きな要素の一つなので、企画段階からしっかりと詰めることが重要」なのです。
■芸能界
これまで次々に新しい挑戦を続けてきたレベルファイブ。ゲームのボイスに人気俳優を起用するのも、その一つです。もっとも『レイトン教授』で大泉洋さんと堀北真希さんが登場した時は「戸外でプレイするDSのゲームでボイスが必用なのか」という声もあったといいます。
しかし日野氏は「ポスト『脳トレ』を考えたとき、カジュアルユーザーのフックが欲しかった」と語りました。そのためパッケージの裏面も俳優のプロフィール写真を使うなど、「女性誌の誌面を彷彿とさせるような内容にした」とのこと。『レイトン教授』が大ヒットしたことで、俳優の起用は同社だけでなく、業界的にも定番のスタイルとなっていきます。
また主題歌においても安易なタイアップは行わず、必ずゲームにあった楽曲を書き下ろしてもらっているそうです。現在はタイトプロとエイベックスの二社を巻き込み、フレームレーベルという新レーベルを設立するまでに至りました。今では「次はどんな世界観で」「どんなアーティストで」と、新作ごとに深いディスカッションが行われるまでになっているそうです。

■映画業界
「『映画「妖怪ウォッチ」誕生の秘密だニャン!』は東宝さんに先物買いをしてもらった・・・」日野氏はこのように振り返ります。
実際『妖怪ウォッチ』はリリース直後から大ヒットしたわけではなく、漫画・テレビアニメなどクロスメディアのピースが埋まっていくなかで、徐々にブレイクしていきました。しかし映画化はリリース直後に決まっていたのです。「必ず当たるから今から制作に入りましょう」という東宝側の一言がきっかけでした。
実際、この判断によって年末商戦の最中に公開でき、東宝映画としては映画『ハウルの動く城』を越える、史上最高のオープニング成績を記録。最終的な興行収入は77億2000万円を記録しました。日野氏は、この背景にあったのが映画『レイトン教授』から続く成功事例の積み重ねだとします。
また日野氏は映画『ALWAYS 三丁目の夕日』などで知られる阿部秀司プロデューサーから、さまざまなことを学んだとあかしました。そして映画の成功にはタイミングが重要であり、その根底にあるものが信頼関係だとしました。
■他業種
『ダーククラウド』『ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君』など、RPGの開発で頭角を現してきたレベルファイブ。その作風が一転したのが『レイトン教授』であり、ベストセラー『頭の体操』シリーズの著者、多湖輝氏との出会いです。ゲーム中に登場するナゾは何人ものパズル作家と合宿で作り上げていき、そのたびにゲームとはまったく異なるクリエイティビティに刺激を受けると言います。
また『レイトン教授』の開発過程で、水平思考を鍛えるパズルブック『ポール・スローンのウミガメのスープ』に注目したという日野氏。そこから 『スローンとマクヘールの謎の物語』 というゲームが誕生し、30万本を越えるヒット作となりました。こうした書籍から着想を受けたゲーム制作も、『妖怪ウォッチ』とは異なるコラボレーションの形だとしました。
■広告代理店
クリエイターとのコラボレーションで最後に紹介されたのが広告代理店です。これまでのコラボがゲームづくりに直接関係するものだったのに対して、こちらは商品ができた後の、販促展開に関するもの。しかもレベルファイブは『レイトン教授』まで自社パブリッシュの経験がなく、最初のうちは広告代理店に対して「どこかで言うとおりに動いてくれるもの」という穿った見方があったといいます。
しかし打ち合わせを進めるうちに、「宣伝だけを考えている人たちのスキルはたしかにすごいものがある」と実感するようになった日野氏。しかし、そうした創造性も発注元であるレベルファイブが上から指示するだけでは、活かしきることができません。とはいえ、最終的な判断は日野氏が行う必要があります。「代理店は責任の代理はしてくれないが、その才能は活かすべき」だと指摘します。
その後、『イナズマイレブン』以降は広告代理店が受け皿となって制作委員会が結成され、クロスメディア戦略の要となっていきます。制作委員会方式は総論賛成・各論反対になりやすいデメリットもありますが、情報の流通や意志決定の判断を早めるための仕組みを、広告代理店のサポートを受けつつ、8年かけて作り上げてきたとのこと。この座組が『妖怪ウォッチ』には不可欠だったと語りました。
■夢はオールジャパンでの世界展開
その後、講演は『妖怪ウォッチ』におけるクロスメディア戦略の解説に移りました。しかし、本稿では冒頭に記したように、「『妖怪メダル』を中核に据えた仕掛け作りがポイントだった」と述べるだけに留めておきましょう。というのも、本講演のキモはそうした「座組」ではなく、そこで実際に行われたクリエイター同士のプライドをかけた「バトル」と、それによって得られた信頼関係にあるからです。
実際に日野氏は「『妖怪ウォッチ』には関係者全員に、自分たちのコンテンツだけでなく、全体でヒットすることを念頭に、作品の本質を考えていく文化がある」と語りました。そのうえで、すべてのビジネスを成功させるための「筋が通った仕掛け作り」がクロスメディア戦略の要だとします。そのためには個々の業界のクリエイターの発想をプロジェクト全体で活かすと共に、コンテンツ貫通プロデューサー(ここでは日野氏)のディレクションが重要だと語りました。
俗にゲーム開発はアートとテクノロジーの融合であり、プログラマー・ゲームデザイナー・アーティスト・サウンドクリエイターという、まったく違う文化や言語を有するクリエイティビティの融合体と言われます。これがマージしているのは、同じ企業という枠組みゆえであることは否定できません。これと同じ雰囲気を、企業の枠を越えて醸造できるか。そこが重要だということなのでしょう。
「コンテンツプロデューサーがしっかりとしたコンセプトを作り、みんなを引っ張らないといけない。その上で各界のクリエイターがアイディアを練り、それぞれの分野でコンテンツを作っていけば、ヒットの確率が上がる」と語る日野氏。その上でいつか世界に通用するクロスメディアを、クリエイター日本代表チームで作りたい。いつかそんなプロジェクトをやりたいと語り、講演を締めくくりました。今後の同社の挑戦に期待しましょう。